あなたは「大爆笑! おもしろ映像集!」といった、インパクトがある映像を特集したテレビ番組を見たことはありますか? 最近多いですよね。私も好きで、ついつい見入ってしまうことが多いです。
その中でも特に、いろんな動物の映像を集めたコーナーはたまりません。私にとっては、とてもいい目の保養になります。ラテやマロンの冷たい視線を時々感じますが…。
そんな動物コーナーの中で時々、散歩中に歩かない状態の犬が引きずられている様子が流れることがあります。テレビ的にはもちろん、パッと見ても犬と飼い主さんのやり取りが面白い光景でもあります。ですが、私はあまりいい気持で見られません。
犬はあきらかに嫌がっています。動かない理由は様々だと思いますが、かわいいラテやマロンを無理矢理引きずるなんて、私にはとてもできません。
でも、散歩中に愛犬が歩かないという悩みは多いですよね。いくらリードを引っ張っても、また声を掛けても動く気配が無い。もしこれが人通りの多い道だったら…。周りの人の目も気になり、とても恥ずかしい気持ちになってしまいますよね。
そこで今回は、愛犬が散歩中に歩かなくなった時の理由や対処法を紹介します。散歩デビューをしたのに歩いてくれないという飼い主さんや、飼い主さん自身がご高齢で愛犬が座り込んだら動かせないという場合にも役立つ方法を紹介します。
散歩中に突然動かなくなる愛犬に困っているという飼い主さんは、ぜひご覧ください!
散歩は必要! ストレス発散に社会化まで

「愛犬が嫌がっているなら、散歩は必要ないのでは」という意見や、「毎日行く必要なんてあるの?」という疑問を持っている飼い主さんも多いのではないでしょうか。
結論を先に言ってしまうと、「散歩は必要。できれば毎日」という言葉になります。
上の記事にもあるように、散歩は愛犬にとって重要なお世話の1つです。その時の天候や時期によって散歩に行かない方がいい時もありますが、基本的には毎日散歩に行った方が愛犬にとってはいいのです。また飼い主さんにとっても、外出して歩くことで気分がリフレッシュし、愛犬との関係もより深めることができます。
ただ、どうしても散歩に行けない時ってありますよね。そんな時は、無理はしないでおきましょう。飼い主さんや愛犬の事情も考えて、どちらも楽しめる時に散歩に出掛けた方がより良い散歩になりますよ。
座り込む! 止まる! 動かない! 愛犬が歩かない6つの理由

散歩中、愛犬が突然座り込んでしまった。動かそうとしても止まってしまい、まったく動く気配が無い。こんな時は本当に困ってしまいますよね。
でも、ここでテレビ番組のように無理矢理引きずってはいけません。嫌がっている愛犬を引きずると、道路との摩擦で犬の肉球がケガを負ってしまうことがあります。さらにそれを続ければ、愛犬と飼い主さんの関係にもヒビが入ってしまうかもしれません。
「でも、早く動いてもらいたいよ!」というのが飼い主さんの本音ですよね。ご安心ください。犬の行動には必ず理由があります。
まずは動かない愛犬の様子を丁寧に観察しましょう。そして、これから紹介するどの理由に近いかを考え、1つずつ対応していきましょう。
歩かない理由1|何かを怖がっている
歩かない理由1つ目は「何かを怖がっている」です。愛犬が尻尾を後ろ足の間に入れ、怯えるように立ち止まってしまった。この場合は、散歩コースにある「何か」を怖がっているのかもしれません。
大きな音と振動が響く工事現場や、小学生の集団、通るたびに吠える近所の犬などが原因で、愛犬が「この先に行くと怖いことがある」と学習しているのです。そうなると怖い物事を避けようとして、あるいは近づかないようにと、その場から動けなくなってしまいます。

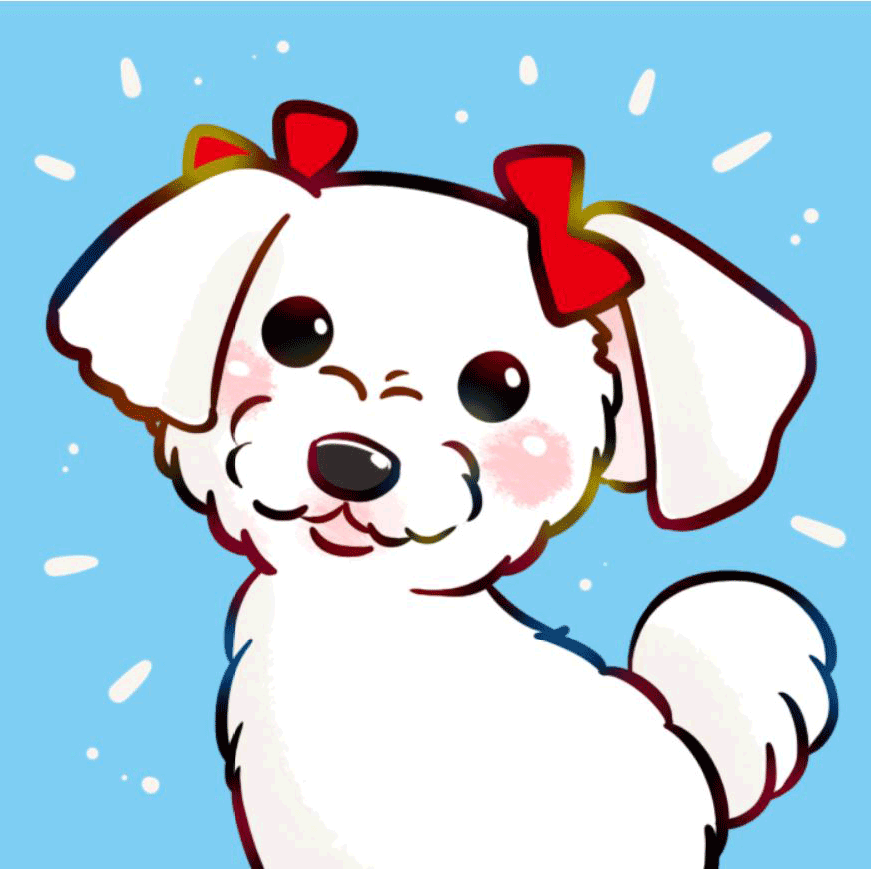
また、散歩デビューしたての犬も散歩自体を怖がって歩かないことがあります。
歩かない理由2|疲れている
歩かない理由2つ目は「疲れている」です。散歩コースを折り返し、散歩が後半に入ったところで愛犬が動かなくなってしまった。それはもしかしたら、愛犬が疲れているサインかもしれません。特に小型犬や老犬に多く見られる理由です。
特に、「ハァハァ」という愛犬の息が非常に荒くなっている場合は、かなり疲れている証拠です。愛犬の体力以上に散歩をしている状態が続くと、骨や関節に異常が起きる可能性もあるので、注意が必要な理由になります。
歩かない理由3|抱っこのしすぎ
歩かない理由3つ目は「抱っこのしすぎ」です。愛犬が「歩かなければ抱っこをしてもらえる」と学習してしまったパターンです。


抱っこされると歩かなくても良くなるので、愛犬は楽になります。そのため歩くのが嫌になると立ち止まり、飼い主の抱っこを要求してくるのです。
これは散歩中に歩かないからと、飼い主さんがすぐに抱っこしてしまう場合に多くなる理由です。座り込めば抱っこをしてもらえると学習しているので、愛犬に怠け癖がついてしまうこともあります。
歩かない理由4|単なるワガママ
歩かない理由4つ目は「単なるワガママ」です。「理由3|抱っこのしすぎ」にも共通する部分があります。
特に、散歩コースを飼い主さんではなく愛犬が自由に決めている場合、愛犬は「散歩の主導権は自分にあるんだ!」と思い込みます。すると自分の行きたくない道、あるいはどうしても行きたい道へ行こうとした際、座り込み動かないことで主張をするのです。
この場合、飼い主さんとの主従関係が逆転しているので、関係を見直す必要があります。

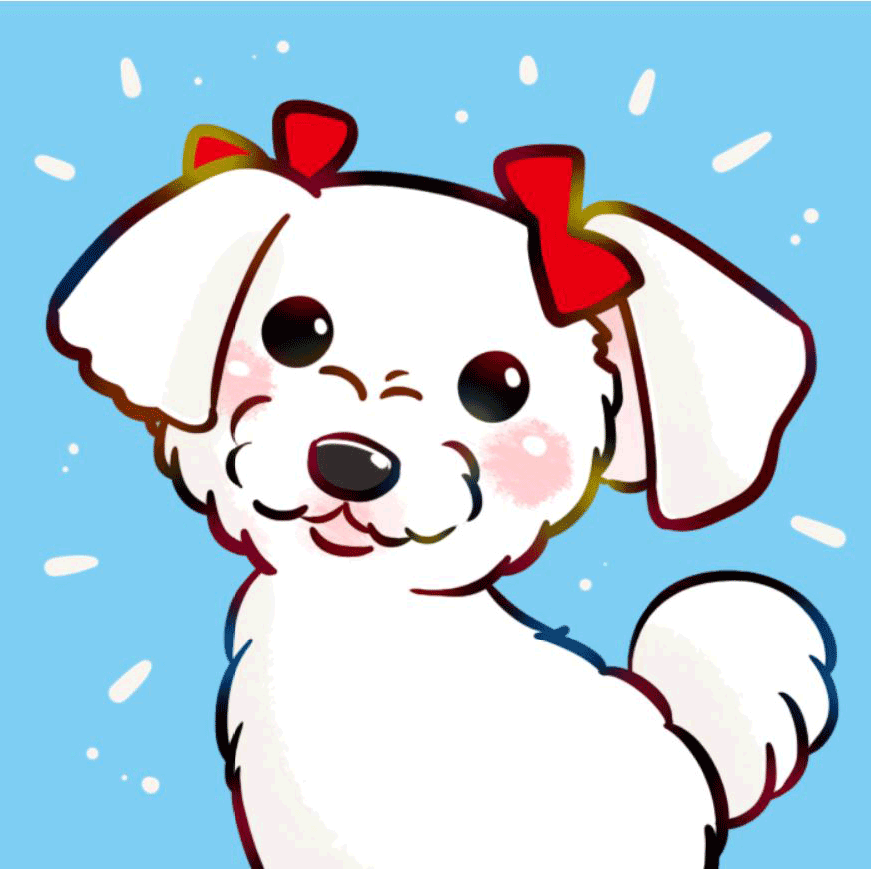



歩かない理由5|楽しいから帰りたくない
歩かない理由5つ目は「楽しいから帰りたくない」です。散歩が楽しすぎて愛犬が「まだ帰りたくない!」と主張している状態です。

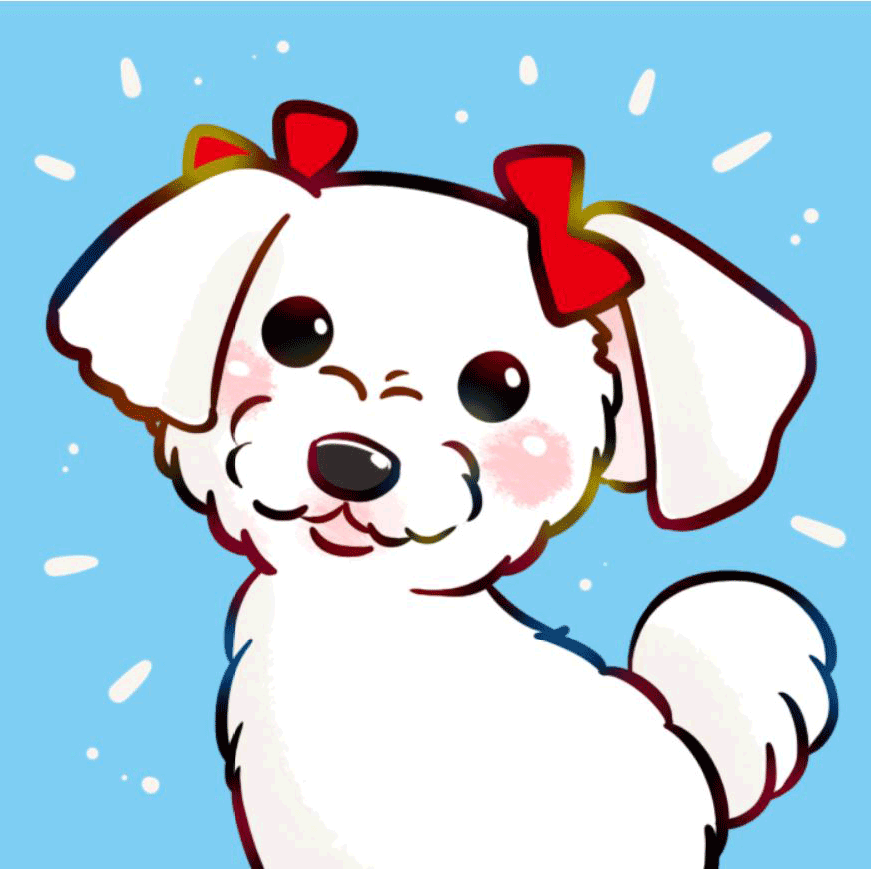


愛犬の行動自体は「理由2|疲れている」と同じく、散歩コースの折り返し地点を過ぎた所で動かなくなることが多いです。違いは、愛犬の息が特に荒くなく、むしろ元気な様子である点です。
この場合、散歩に運動の要素を追加することで愛犬も満足することが多くなります。
歩かない理由6|病気・ケガをしている
歩かない理由6つ目は「病気・ケガをしている」です。これは一番気をつけなければいけない理由です。
愛犬が突然立ち止まったと思ったら、スキップして歩くようになった。これは、愛犬の足に何かしらの異常が発生した可能性があります。特に真夏や真冬の散歩で愛犬が犬用の靴をはいていない場合、肉球がヤケドなどの怪我を負い、痛くてスキップしていることが考えられるのです。
また、散歩中急に歩かなくなるということが続いているなら、愛犬が心臓病や関節の病気で歩くのが辛くなっているのかもしれません。
いずれの場合も、愛犬が辛そうにしていたら急いで動物病院で診てもらうようにしましょう。
愛犬を再び歩かせる! 効果的な5つの方法

ここまで、愛犬が歩かなくなる理由を紹介しました。思い当たる部分はありましたか?
ここからは、歩かない愛犬を再び歩かせる方法を紹介します。愛犬に合った方法を試してみてください。
歩かせる方法1|散歩ルートを変えてみる
歩かせる方法1つ目は「散歩ルートを変えてみる」です。これは「歩かない理由1|何かに怖がっている」に、特に有効な方法です。怖がっている対象から離れることで、愛犬も素直に歩き始めることが多くなります。
散歩ルートで必ず出会ってしまう存在はもちろん、不意に出会ってしまった場合でも、愛犬が怖がるような様子を見せたらすぐに方向転換をしてそこから立ち去るようにしましょう。そうすると愛犬も安心するので、散歩をスムーズに行うことができます。
散歩コースが複数確保できる飼い主さんにオススメの方法でもあります。
歩かせる方法2|リードを後ろに引っ張る
歩かせる方法2つ目は「リードを後ろに引っ張る」です。これはどんな理由でも有効な方法です。また、かける力が少なめなので飼い主さんがご高齢の場合でも役立ちます。
まずは、実際にこの方法を行っている動画をご覧ください。
動画では少し強めにリードを引っ張っていますが、リードは前方に引っ張るのではなく、愛犬の後方に引っ張るようにしていますよね。すると、座っている愛犬も足が自然に浮いて立ち上がるのです。立ち上がったら、前方にリードを引き散歩を続けましょう。
なかなか立ち上がらない場合は、これを何回か繰り返し、犬が立ち上がるまで根気よく行います。また、犬が立ち止まりそうになったらリードを横に引いて曲がり、別の方向に行くのもいい方法です。
歩かせる方法3|すぐに抱っこをしない
歩かせる方法3つ目は「すぐに抱っこをしない」です。これは「歩かない理由3|抱っこのしすぎ」や「歩かない理由4|単なるワガママ」に有効な方法です。
この場合、「歩かなければ抱っこをしてもらえる」という、愛犬の中の条件付けを無くさないといけません。そのため、愛犬が歩かなくなったらすぐに抱っこをするのではなく、まずは「歩かせる方法2|リードを後ろに引っ張る」を試してみましょう。
それでもダメな場合は、散歩自体を見直すようにします。愛犬自身が散歩を嫌いということもあるので、まずはそれを解消するよう心掛けましょう。
最初は公園などでリードをつけたまま自由に歩かせます。慣れてきたら公園の周囲の道に出てみましょう。愛犬が怖がらず、公園にいた時のように歩けばオーケーです。それにも慣れてきたようなら、公園から離れた道で散歩をしてみましょう。
こういった具合にステップを踏んで、散歩の楽しさを愛犬に体験させるのがポイントです。自分の足で歩く散歩の楽しさが分かれば、愛犬の抱っこ癖は自然に無くなるはずです。
歩かせる方法4|「待て」を指示する
歩かせる方法4つ目は「『待て』を指示する」です。

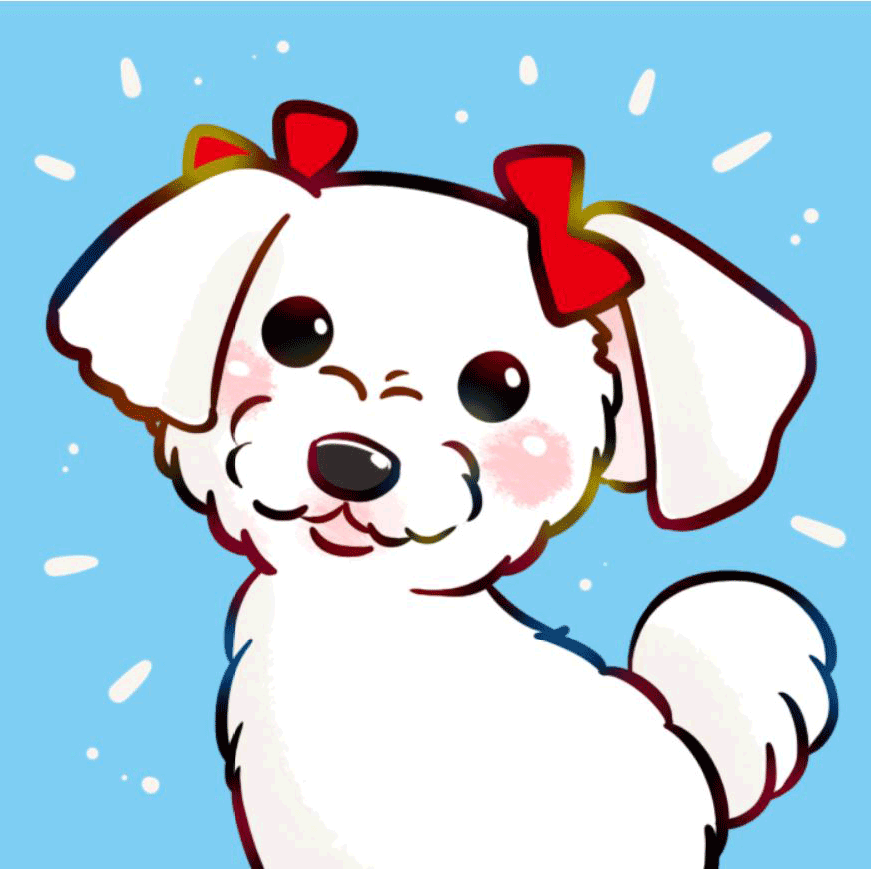
マロンやラテのように驚かれた飼い主さんもいますよね。


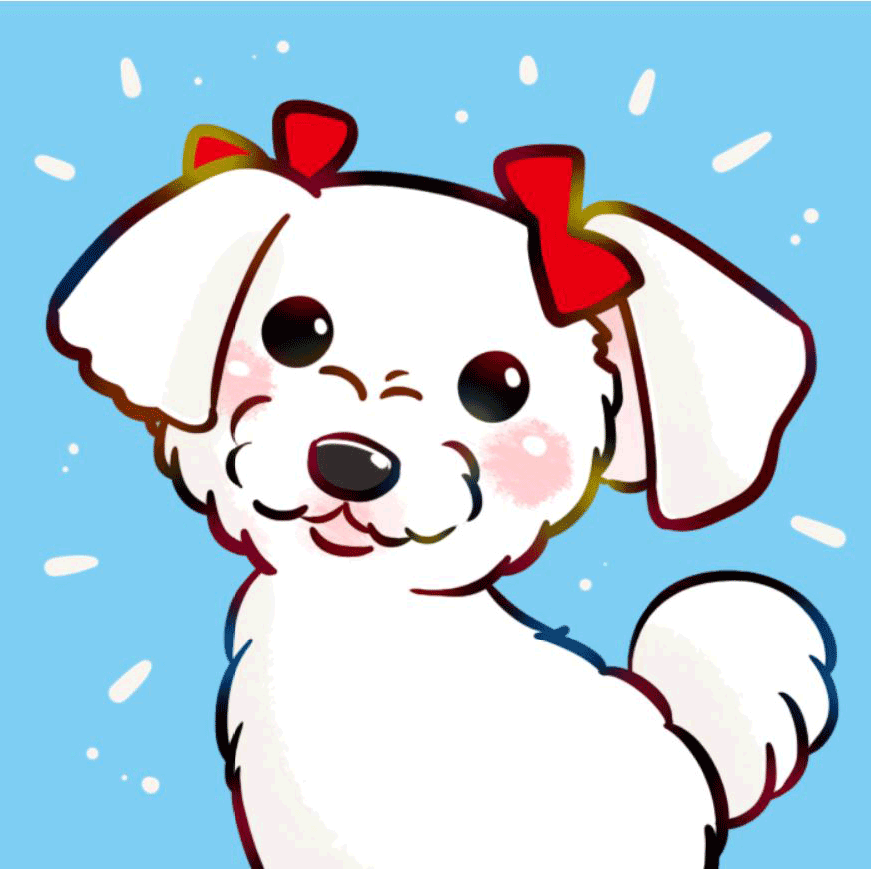
童話「北風と太陽」のお話はご存知ですか? 下の動画で話の流れが見られます。
これを飼い主さんの行動に当てはめると、「愛犬のリードをグイグイと引っ張る行動」が北風に、「愛犬に『待て』と指示すること」が太陽になります。
北風のように愛犬を強引に従わせようとリードを引っ張っても、愛犬はそれに反発し余計に動かなくなります。そこで、太陽のようにあえて「待て」という温かい指示を出すのです。
「待て」を指示することで、愛犬が自分の意思で動かないという状態から、飼い主さんの命令で動かないという状態に移行させます。しばらくしてから「よし!」と待てを解除すると、愛犬は反射的に立ち上がり、少し前に進むようになります。
これを繰り返していると、愛犬は「もう素直に歩きたいよ」と感じ、歩かない状態が減っていくのです。
ただしこの方法を行うには、基本的なしつけがしっかりされていることが条件になります。散歩に行く前に、「待て」を含めたしつけが十分に行えるようにしておきましょう。
歩かせる方法5|主従関係をはっきりさせておく
歩かせる方法5つ目は「主従関係をはっきりさせておく」です。これは散歩に行く前の段階で行うしつけになります。
散歩コースを愛犬が自由に決めている、すぐに抱っこを要求してくるといった場合、愛犬との主従関係が逆転している可能性があります。それらを解消するためにも、主従関係を見直す必要があるのです。
主従関係を見直す際に有効なのが「リーダーウォーク」です。リーダーウォークができるようになれば、愛犬は自然と飼い主さんがリーダーだと認めるので、散歩中なのに歩かないという行動がグッと減ります。ぜひリーダーウォークを身につけてみてください。
世代別! 歩かない時の対処法

ここまで、散歩中に動かなくなってしまった愛犬を、再び歩かせる方法を紹介してきました。
ただ、犬の年齢によっても歩かない理由がそれぞれあります。最後に犬の世代別に歩かない時の対処法を紹介しますね。
子犬~散歩デビューしたけど歩かない!
「散歩デビューをしたのに愛犬が歩かない」という、犬を飼い始めたばかりで悩んでいる方は多いのではないでしょうか? 実際、私もラテやマロンを飼い始めた時はそうでした。

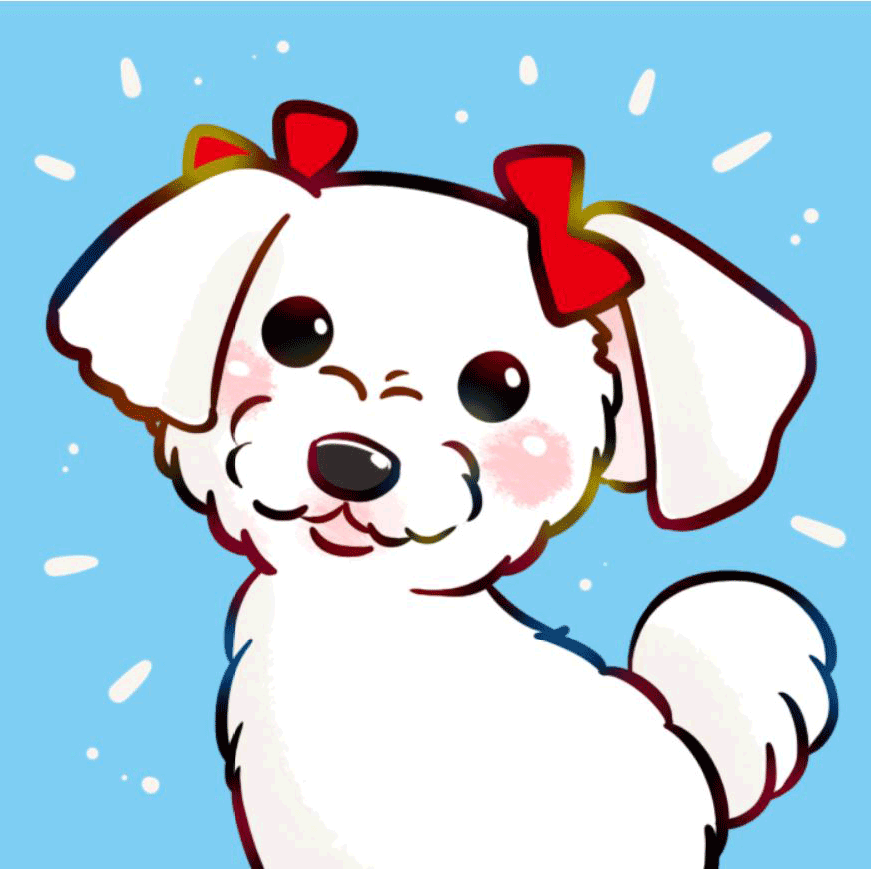

実は子犬の場合、散歩デビューですんなりと歩く方が少ないと言われています。初めての場所にいきなり出されるわけですから、ラテやマロンのように不安や緊張の方が勝ってしまうのです。
子犬が散歩デビューで歩かない場合、まずは愛犬を抱っこした状態で散歩をしてみましょう。はじめは家の周囲を抱っこしながら歩き、外の刺激に愛犬を慣れさせます。それからは少しずつ家から離れ、散歩の時間も伸ばしていきます。こうすることで愛犬も外の刺激に慣れ、地面を歩く散歩になっても大きな不安や緊張が無くなるのです。
子犬の社会性を育てるためにも散歩は必要です。まずは外の刺激に慣れさせるところから始めてみましょう。
成犬~散歩に慣れてきたからこそ
成犬が散歩時に歩かないという理由は、これまで紹介してきたものが当てはまります。
ただ、散歩に慣れてきたからこそ、飼い主さんとの主従関係があいまいになってしまうこともあります。そんな時は改めてリーダーウォークを行うなど、飼い主さんとの関係を見直してみましょう。
また、愛犬が散歩に満足していないようだったら、運動の要素を多く取り入れてみる、また散歩コース自体を変えてみるなど、新しい刺激を取り入れるようにしてみましょう。そうすることで、愛犬も新鮮な気持ちで散歩を楽しむことができます。
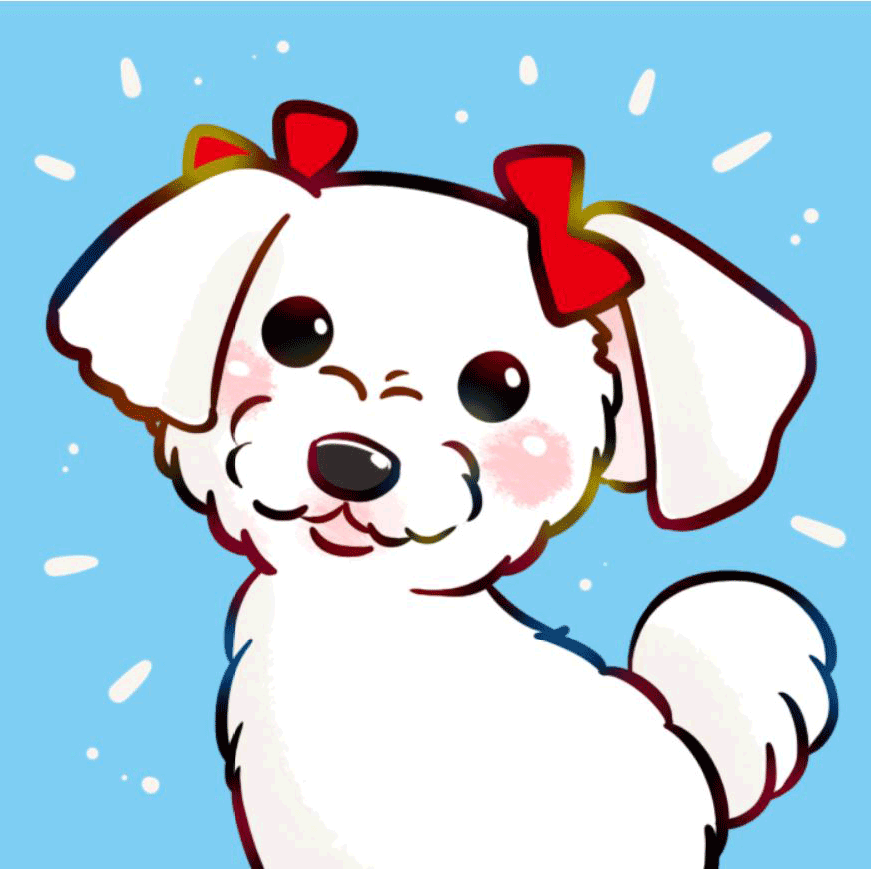


老犬~散歩時間や距離を見直す
老犬になると、体の面でも心の面でも不調が現れます。体の面では歩くと足が痛む、また動くこと自体が辛いから歩かなくなるといったことが起こり、心の面では散歩に出掛けても散歩を楽しむ意欲が無くなってしまうといったことが、歩かなくなる原因として考えられます。
そのため愛犬が高齢になったら、散歩は愛犬のペースに合わせてあげましょう。歩く速度をゆっくりにする、また散歩時間や距離を短くするなど、愛犬をよく観察しながら最適な散歩のペースを見つけてあげてください。
もちろん、それでも散歩を嫌がるようでしたら、動物病院へ行って心身の不調がないかどうか診てもらうようにしましょう。
まとめ
ここまで、散歩時に愛犬が歩かない理由やその対処法を紹介してきました。まとめると以下のようになります。これまでを思い出しながら読んでみましょう。
- 散歩は最高のリフレッシュ!愛犬と一緒に楽しもう!
- 愛犬が動かない理由を知っておこう
- 再び歩かせるように方法を工夫してみよう!
- 愛犬の年代に合った対処法を試してみよう
愛犬が散歩中に歩かなくなるのには、必ず何か理由があります。無理に引きずるのではなく、愛犬の様子をよく観察して理由を突き止めましょう。そして理由が分かったら、愛犬が心から散歩を楽しめるよう積極的に解消しましょう。
でも、愛犬が散歩に出掛ける前から散歩を嫌がっている時は、散歩をさせないという選択肢もあります。愛犬に無理をさせない、また飼い主さんも無理をしないことが大切ですよ。
愛犬と飼い主さんの両方がストレスにならないベストな方法を見つけ、散歩を軽やかな足取りで楽しみましょう!
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。この記事が、あなたと愛犬の散歩が楽しいものになる手助けになれば幸いです。

















