「犬は散歩が好き」というのは、ほとんどのわんちゃんに当てはまります。私の飼っているラテとマロンも、私がリードなどの散歩セットを取り出すと、尻尾をパタパタと振って目がキラキラと輝きます。その様子はずっと見ていたいのですが、あまり待たせるとラテから「キャン!」と催促されるので、待たせるのはほどほどにしています。
散歩はわんちゃんと絆を深めるのにも役立ちますが、その散歩が悩みの種という飼い主さんもいます。そう、わんちゃんの「吠える癖」です。
家の中では吠えないのに、いざ散歩に連れて行くと人や車に吠えてばかり。注意しても治まらず、周囲の人の目が気になって、散歩を途中で中断して帰宅してしまう。これだと、飼い主さんは恥ずかしい思いをしてしまいますよね。
でも、吠えているわんちゃんの気持ちを考えたことはありますか。わんちゃんが吠える状況が続くと、もしかしたらわんちゃんも散歩を嫌いになってしまうかもしれません。そうなったらわんちゃんの健康にも影響が出てしまいます。
そうならないためにも、わんちゃんが吠える理由と原因を知りましょう。そしてそれに合った対策をして、改めて飼い主さんにとってもわんちゃんにとっても散歩を楽しいものにしましょう。
うちの愛犬はどれ?散歩で吠える理由を知ろう
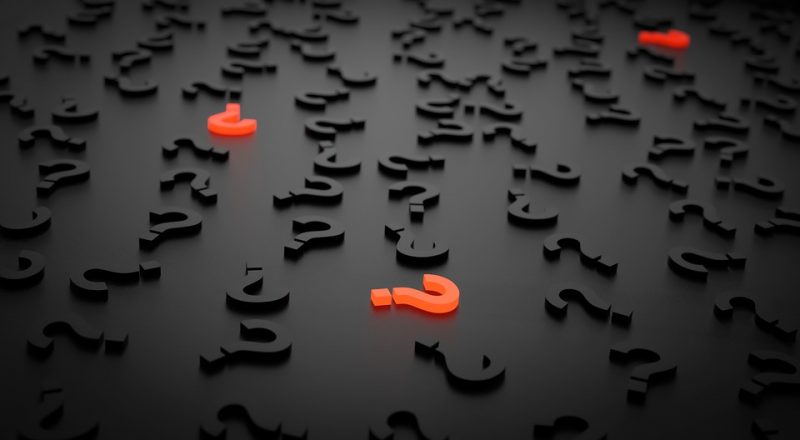
一口にわんちゃんが散歩で吠えるといっても、その理由は様々です。ここでは代表的な理由を3つご紹介します。
「警戒」して吠える


愛犬が歯をむき出し、凄い勢いで吠えている時は、その吠えている物事に対して警戒して吠えている可能性が高いです。「こっちに来ないで!」と威嚇しているんですね。
この場合、愛犬は「リーダーは自分だ」と思い込んでいて、飼い主さんや家族を他の人やわんちゃんから守ろうとしていると考えられます。そのため、自分のテリトリーや縄張りに入ってきた他の人や犬に対して攻撃的に吠えるのです。
ただこれがエスカレートすると、他の人やわんちゃんに対して実際に攻撃をすることもあるので、なるべく早く解消したい吠え癖の一つです。
「恐怖」で吠える


愛犬の吠え声がやや高く、後ずさりや尻込みしながら吠えていたら、愛犬はその物事に対して恐怖で吠えている可能性が高いです。「こっちに来ないで!」と、今度は怯えているんですね。
子犬の頃の早い時期に母犬から引き離されてしまった、また、愛犬が飼い主さんやその家族とだけ接していて、他の人やわんちゃんとのコミュニケーションが不足していたということが考えられます。
また吠える物事に対して、以前嫌な思いをした経験がある場合、それが愛犬の恐怖に繋がっている可能性もあります。
嬉しさから「興奮」して吠える
上の2つがマイナスな感情から吠えているのに対して、こちらは嬉しい・楽しいといったプラスの感情が高まって吠えているパターンです。あまりの嬉しさから興奮して吠えてしまうんです。
飼い主さんが、仕事など長い留守から帰ってきた時に愛犬に吠えられるのは、主にこれが理由です。また、愛犬が遊んでいる最中に吠えてしまうのも、テンションが高くなって興奮していることが考えられます。
散歩の時も、愛犬の目の前にその子をかわいがってくれる人や仲の良いわんちゃんが現れたら吠えてはいませんか。それは会えた嬉しさから興奮して吠えているのです。


散歩のどの時点で吠える?状況でしつけを変えよう

わんちゃんが吠える理由はご理解いただけたでしょうか。ここからは、わんちゃんが散歩のどのタイミングで吠えるかを思い出しながら読み進めてください。
「散歩で吠える」といっても、散歩のどのタイミングで吠えるのかによって、しつけの仕方が分かれます。ここでは大きく3つのタイミングに分けてみました。
散歩する前に吠える
愛犬の散歩に行こうと、リードやエチケット袋などの散歩セットを取り出すと、凄い勢いで吠えだしてしまう。これは、上で挙げた「嬉しさから興奮して吠える」のパターンがほとんどです。
「リード=楽しい散歩」という関連付けが愛犬の中に出来上がっていて、興奮を抑えられず吠えてしまうのです。
これを抑えるには、リードを散歩以外の時にもつける方法が有効です。飼い主さんがトイレに行く時や、愛犬のブラッシング時など、散歩時以外の何でもない時に着けることがポイントです。
これをしばらく続けることで、愛犬の中の「リード=楽しい散歩」という条件付けが薄くなり、リードをつけるのが当たり前になります。そうなると、本当に散歩に行く時もあまり興奮せず、吠える回数が少なくなりスムーズに散歩へ行けます。愛犬自身も、落ち着くことで余計な体力を使うことがないので、散歩に集中できます。
散歩の時だけ吠える
もっとも多い悩みが、この「散歩中に吠える」ことではないでしょうか。家ではおとなしい愛犬が、一歩外へ出ると性格が変わってしまったかのように吠えだしてしまう。通りかかる人はもちろん、車や自転車、そして他のわんちゃんにも吠えてしまい、周囲に対して申し訳ない気持ちでいっぱいになってしまいますよね。
これは、上で挙げた「警戒して吠える」と「恐怖で吠える」のパターンが主に当てはまります。
「警戒して吠える」のは、飼い主さんを守ろうとしていると考えられるので、愛犬との関係をもう一度見直すことが必要です。
「恐怖で吠える」のは、散歩コースにある「何か」を怖がっていると考えられるので、散歩コースを変えたり、恐怖の対象が分かればそのものを避けたりすることが有効です。
いずれにしても「警戒」や「恐怖」が長く続くと、愛犬は散歩を嫌がるようになります。そうならないためにも吠える原因をしっかり理解しておきましょう。
散歩中、どの物事に対して吠えるかによってもしつけはことなります。詳細は次の章でお話ししますね。
散歩が終わってから吠える
散歩前・散歩中はおとなしいのに、散歩が終わって家に帰ってきた途端愛犬が吠えだすという場合もあります。これは上で挙げた「興奮して吠える」に近いパターンです。ただ、正確には「刺激的な世界からの興奮が抑えられず吠える」という状態です。
散歩はわんちゃんにとって、とても刺激的な体験です。同じ散歩コースでも通る車は毎回違いますし、天気だって昨日と今日では違っているかもしれません。それらの刺激を受けた愛犬は、その刺激からの興奮が家に帰っても冷めず、家の中でも吠えてしまうのです。
対処法ですが、まず愛犬の動きを止めましょう。「お座り」や「伏せ」、「待て」の指示を出して、愛犬の動きを制止させるのです。しばらくその状態を続けると、徐々に愛犬の興奮も治まってきます。様子が落ち着いてきたなと感じたら、指示を解除してあげましょう。
また、この指示は静かな家の中だけでなく、ドッグランなど他のわんちゃんがいる場所や人通りの多い街中でも行うと、愛犬を飼い主さんに集中させるトレーニングにもなるのでより効果的です。
散歩中でも大丈夫!原因別にしつけをしよう

ここからは、もっとも悩みが多い散歩中に吠えてしまう状態を掘り下げていきます。散歩中にわんちゃんが吠える原因別に、行うと効果的なしつけを紹介します。
人や他のわんちゃんに対して吠える
人や他のわんちゃんに対して吠えるのは、「興奮」の場合もありますが、「警戒」や「恐怖」から吠えている場合が多いです。
「警戒」から吠えている場合、飼い主さんを守っている、または自分のテリトリーを守ろうとしているなど、愛犬は何かを「守ろう」としています。このような「守ろう」という意識を愛犬が持ってしまうのは、飼い主さんとの主従関係が逆転しており、愛犬が「自分がリーダーなんだ」と思っていることが多いのです。
この「わんちゃんのリーダー意識」を解消すれば、「警戒」の吠え癖はなくなります。そこでオススメするのが「リーダーウォーク」です。
リーダーウォークを身につけると、愛犬は「飼い主さんがリーダーなんだ」と認識するので、散歩中も飼い主さんに意識が向くようになります。そのため、飼い主さんが警戒しないものには愛犬も警戒しなくなり、警戒から吠えるという行動が減っていくのです。
「いきなりリーダーウォークから入るのは難しいかな…」という飼い主さんは、「伏せ」や「待て」が普通に行えるようトレーニングしてみましょう。これらができてからリーダーウォークのトレーニングに入ることで、愛犬はよりスムーズに覚えることができます。
また、愛犬を安心させるために、その警戒する対象に徐々に慣れさせることも大切です。特に吠える相手が他のわんちゃんだった場合、慣れないとわんちゃん同士のケンカになってしまうこともあります。そうならないためにも、他のわんちゃんには早めに慣れてもらいましょう。
方法の1つとして「実際にわんちゃんに協力してもらう」ことがあります。
この方法のポイントは「あまり吠えない、穏やかなわんちゃん」に協力してもらうことです。穏やかで余裕のあるわんちゃんと一緒にいることで、愛犬は他のわんちゃんと一緒にいる状況に慣れていきます。その状況を保ったまま、穏やかなわんちゃんと愛犬との距離を徐々に詰めていきましょう。焦らず少しずつ距離を詰め、最終的にはそのわんちゃんの隣まで行くことを目標にします。
その目標が達成できたら、今度はもう少したくさんのわんちゃんがいる状況に慣れさせます。このような感じで、徐々にステップアップして愛犬の警戒心を解いていきましょう。
警戒の対象から遠ざかってばかりだと、愛犬は「吠えれば遠ざけられるんだ!」と学習してしまいます。そうならないためにも、早い段階から他の人やわんちゃんに慣れさせるようにしましょう。


もう一つの「恐怖」から吠えている場合ですが、こちらのしつけには注意が必要です。「恐怖」から吠えている場合、「警戒」とは逆の対応をする必要があるからです。
愛犬を安心させる点は同じですが、愛犬が恐怖を感じている対象にはなるべく近づかないようにすることが基本です。克服させようと飼い主さんが無理矢理近づくと、愛犬はますます怖がって吠えてしまうからです。
一番の方法は「散歩コースを変えること」です。散歩コースを変えることで恐怖の対象である人や他のわんちゃんを避けられる場合は、変えることをおすすめします。
散歩コースを変えられず、どうしても恐怖の対象に会ってしまう場合は、その対象が愛犬の視界に入る前におやつやおもちゃなどで愛犬の気をそらし、何事も無くスルーしてもいいです。愛犬が対象に気づかない内に気をそらすのがポイントです。
それでも突発的に出会ってしまった場合は、その対象と大きく距離を取り、静かにその場を離れるようにしましょう。来た道を戻るという方法もあります。


「警戒」と「恐怖」を見分けるには、愛犬の様子をよく観察することが大事です。最初の方で挙げたように、歯をむき出して勢いよく吠えている場合は「警戒」、吠え声が高く怯えるような様子の場合は「恐怖」である可能性が高いです。愛犬を落ち着かせるのと同時に、どんな気持ちで吠えているのかも理解できるようになりましょう。
車やバイクなど動くものに対して吠える
車やバイクなど、機械的な動く物に対して吠える場合は、「警戒」や「恐怖」の他に「興奮」の要素も加わります。
「警戒」や「恐怖」の場合は、上で挙げた「人や他のわんちゃんに対して吠える」場合の対処法と同じです。ただ「興奮」で吠えている場合は、犬本来の狩猟本能が関係してきます。特に牧羊犬として活躍している犬種は、この動く物に興奮して吠える傾向が強くなります。
対処法としては、まず愛犬を落ち着かせるために「お座り」や「伏せ」の指示を出します。そのまま興奮の対象である車やバイクなどが通り過ぎるのを待ち、愛犬がおとなしくしていたらたくさん褒めるようにしましょう。そうすることで愛犬は「おとなしくしていれば褒めてもらえるんだ!」と学習します。
また、最初は車通りの少ない道から始めて徐々に大通りへと移行していくと、愛犬もストレスなくステップアップできます。こちらも焦らず、少しずつトレーニングするようにしましょう。
逆にわんちゃんに吠えられた時は?

自分が犬を連れている・連れていないにかかわらず、散歩中のわんちゃんに吠えられてしまったという経験がある人は多いのではないでしょうか。これまで書いたようにわんちゃんやその飼い主さん側が原因という場合もありますが、吠えられた自分に原因があることも少なくありません。
たとえば、わんちゃんが緊張状態にある時にいきなり近づいて頭を撫でた、かわいいわんちゃんに興奮して大きな声を出した、また自分が過去に怖い思いをしたため、わんちゃんに対して怖がっている様子を見せたなど、どれもわんちゃんに吠えられる原因になります。
いずれの場合も、まずわんちゃんに敵意を見せないことが大切です。
いきなり近づいて頭を撫でるのではなく、わんちゃんの方から近づいてくるのを待つ、あるいは飼い主さんに「触ってもいいですか?」と許可をもらってから触ることが、マナーとしても大事なことです。また、自分が犬嫌いだったとしたら、慌てるそぶりを見せず、なるべく平静を保って静かにその場を離れるという方法が有効です。
わんちゃんも相手に敵意が無いと分かれば、自分の方から近づいて挨拶をしてくれるはずです。わんちゃんと仲良くなりたいという方は、そのわんちゃんが近づいてくるまで気長に待ちましょう。



それでも散歩中に吠える時は?

これまで紹介した対処法を実践してもわんちゃんが吠え止まない、または原因が分からないという時は、無理せずしつけの専門家にお願いしましょう。特にまだわんちゃんが幼い時期に依頼すれば、わんちゃんもしっかり理解でき、その後のしつけもスムーズに行うことができます。
また、それでも散歩中に吠える癖が治まらない時は、体や心に病気を抱えていることが考えられます。一度動物病院へ行って獣医師さんに相談してみましょう。
まとめ
ここまで、散歩中に愛犬が吠える理由や、原因別のしつけについて紹介しました。もう一度確認してみましょう。
- わんちゃんが吠える理由を知ってからしつけよう
- 散歩のどのタイミングで吠えるかを把握しよう
- わんちゃんとの関係を再確認して、原因別に対処しよう
- 無理は禁物!プロにも頼ってみよう
散歩はわんちゃんにとって楽しみの一つです。その楽しみが苦しみになって散歩が嫌いにならないよう、まずはわんちゃんを落ち着かせるところから始めてみましょう。
そのためにも、わんちゃんとの主従関係をしっかり作り直すことが重要です。飼い主さんは「自分がリーダーなんだ」という自覚を持ち、わんちゃんに対しては厳しさと優しさを併せ持った態度で接しましょう。
また、散歩は飼い主さんとわんちゃんの関係を見直すいい機会でもあります。怖がらず、勇気を出して外へ出掛けてみましょう。そして散歩コースをレッドカーペットと思って、堂々とわんちゃんをアピールしちゃいましょう。














