愛犬と暮らす生活の中で、今まではちゃんと大人しくしていたわんちゃんが急に吠えるようになった経験ってありませんか?
一概に吠えると言っても、犬にとっては様々な理由があります。飼い主さんが吠えること=うるさい、悪いことと認識していると、わんちゃんが送っている大切なメッセージを見失ってしまうでしょう。
犬は人間の赤ちゃんと一緒で、言葉は喋れはしないものの、「吠える、鳴く」ことで、主張や感情表現をします。例えば、お腹が空いたりどこか痛いところがあると、鳴いてそれを飼い主さんに訴えようとします。
以前、マロンが吠えているのにただ無駄吠えだと思っていたら、実は怪我で苦しんでいた。ということがありました。そういったときにいち早く異変を見つけてあげられることが飼い主にとっても重要なことですよね。
この記事では、主に病気になってしまった犬や老犬が吠える理由について紹介していきます。わんちゃんの大切な健康の為にも目を通していただけると幸いです。
何に対して吠えてるの?本当は無駄吠えなんてなかった

人間が言葉で話をするように、犬も吠えて何かを「主張している」「訴えている」ので、決して無駄に吠えているわけではないのです。例えば、人間でいうと「お腹すいた〜(要求吠え)」「なんだかお腹が痛むな…(痛み吠え)」などといったことを、犬は吠えることで表しています。




マロンとラテのように、犬側からしてみればただ無駄に吠えているわけではなく、今抱えている気持ち、感情を訴えているのです。
このように犬が吠えるのにはきちんと理由があるので、「無駄吠え」と捉えることは間違いで、なぜこのタイミングで吠えているのか?とまずはわんちゃんが吠える状況を観察してみるのも大切です。

以下の記事では、吠え方の種類から状況別の対処法まで詳しくご紹介しています。病気ではないわんちゃんでも、普段の生活で飼い主さんに訴えかけたいことを抱えている場合がたくさんあります。是非こちらの記事もご一読ください!
病気の予防の為に日頃から健康チェックを行おう!

まずは犬が普段生活している環境を一度見直してみましょう。忙しさを理由に、ケージの中が不衛生になってしまっていたり、体重が増えてきたのに適切な食事の量が与えられていなかったり、気づけば当てはまることがあるかもしれません。
以下に犬の健康管理チェックリストを記載しましたので、早速チェックしていきましょう。
- 快適で衛生的な生活空間がある
- バランスのとれた食事が与えられている
- 定期的に健康管理が行われ、身体が健康である
- 犬のエネルギーを発散させ、運動欲求を満たしている
- 社会的なかかわりを持っている
犬の病気の予防の為に、必要なのは①〜③です。
例えば、木製のケージを使用していた場合、犬がかじって表面の塗装がボロボロと剥げてしまい、付着した唾液から細菌が繁殖しやすくなります。また、その箇所にマーキングしたりすると尿が付着した箇所からさらに不衛生な状態になり、カビが生えたりすることも。
そんなところをわんちゃんが舐めたりしたら病気の元となるのは一目瞭然ですよね。
また、②においてはおやつをあげすぎたり、おねだりされたからといって、人間の食べる料理の一部をあげたりせず、体重に従い適量のドッグフードを与えることに気をつけましょう。
③は定期的に動物病院に連れていって健康チェックしてあげるのが良いと思います。歯磨きなど、普段からできることもしっかりと行っていきましょう。
そんな中でも④と⑤は特に吠えの予防に重要な項目になっています。犬はエネルギーをもてあますとよく吠えるようになります。④のように、犬のストレス発散と運動不足解消は日頃から心がけるようにしましょう。
⑤の社会的なかかわりというのは、散歩で家の外に出て他のわんちゃんや道行く人と関わったりすることで、閉鎖的な家の中でのストレスを解消させることができるので、これも重要になってきます。
犬が急に吠えるようになったら病気も疑って!

冒頭でも挙げたように、わんちゃんが急に吠えるようになったら、もしかすると何らかの痛みを訴えていることがあるかもしれません。
声がかすれている、よく咳をするようになったなど、いつもと様子がおかしいなと少しでも感じたら、手遅れにならない為にもすぐに動物病院へ連れていくことをおすすめします。

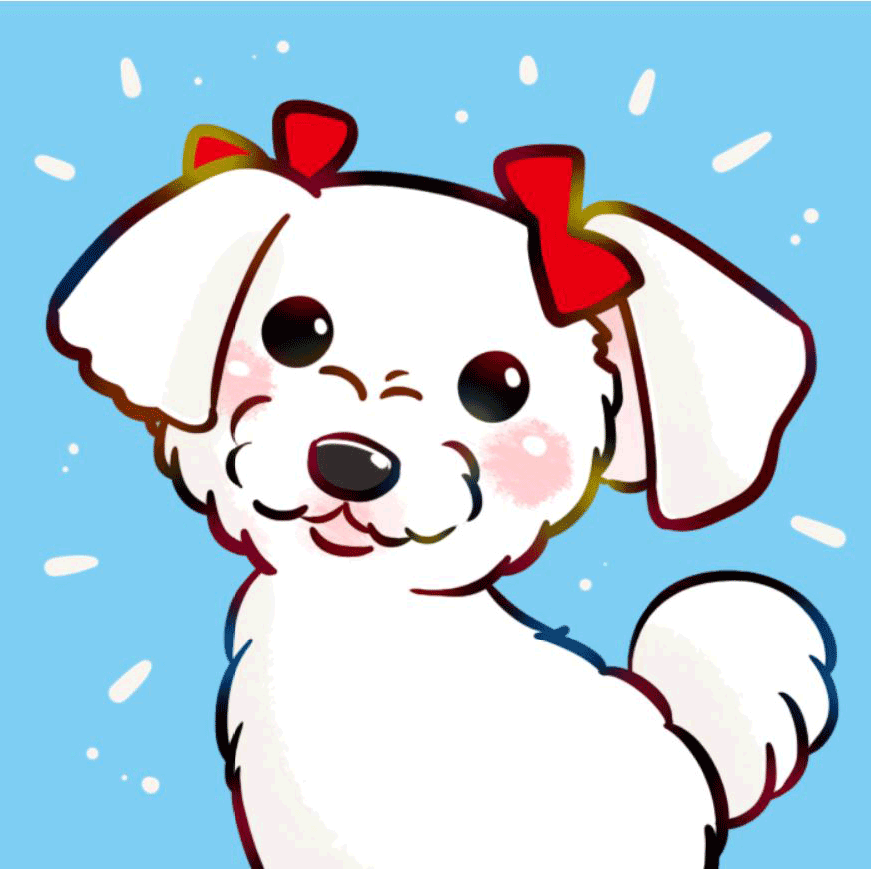

慢性気管支炎のために咳をする場合
犬の慢性気管支炎の症状としては、過去1年間に少なくとも2カ月連続して咳が続きます。気管支内に持続的な感染あるいは空中刺激物の慢性吸入により、過度に粘稠な粘液や膿汁が存在し、さまざまな病態が起こります。
- 飼育環境を整える
- 空気清浄機の設置、掃除機をまめにかける
- 過度なストレスは避ける
- ダニ・埃などのアレルゲンは避ける
また、似たような症状で気管虚脱という病気を発症している可能性もあるので、どちらにしても速やかに動物病院へ向かってください。
骨折、脱臼、関節の痛みなどによって吠える場合
「キャンキャン」鳴いたり、かすれた鳴き声をしたときに少しの動きでも痛がって鳴くようなら、犬が関節や骨に痛みを感じている可能性があります。また、痛みのあまり吠えたり暴れたりすることがあります。
この場合は、鳴き声+痛がる動きがあるので分かりやすいかと思いますが、わんちゃんからのSOSを察知したら至急、動物病院へ連れて行ってあげてください。
骨折の場合
- 折れた足を上げたまま歩く
- スキップするように歩く
- 患部を触らせようとしない
- 足が通常とは違う形に変形してしまっている
これらの症状を発見したら骨折を疑いましょう。
一言で骨折といっても、事故やけんかなどで骨折してしまう場合(外傷)や、骨の腫瘍などで骨が弱くなって折れてしまう場合(病的骨折)、また、弱い力が同じ場所に加わり続ける事で骨折してしまう場合(疲労骨折)などがあります。
外傷によって骨折する原因としては、他の犬や動物との喧嘩、交通事故や落下などが多いようです。落下においては、幼犬や小型犬では10cmの高さでも骨折することがあるので、家の中でも高さがある部分には注意しましょう。
治療法としては、骨折の場合、ギプスや副木による固定で骨を癒合させますが、それらでの癒合が難しいと考えられる場合には、手術が選択されます。
脱臼の場合
- 足を引きずる
- 曲げにくそうにしている
上記が当てはまる場合は「脱臼」しているかもしれません。
脱臼とは、高いところから飛び降りたり、ジャンプしたり、激しく転んだりすると、関節の可動域を超えてしまうことが原因で、骨の関節が本来の位置からずれてしまった状態を言います。
すべての犬種で脱臼が起こる可能性がありますが、中でもトイプードルやチワワ、ヨークシャテリアなどの小型犬が脱臼しやすいと言われています。中でも犬に多いのは「膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)」です。膝蓋骨とは、一般的に「膝のお皿」の部分です。
膝蓋骨脱臼の治療は、内科的治療と外科的治療があり、 内科的治療は、内服薬やサプリメント、半導体レーザー治療などです。また、獣医さんから運動制限や体重制限などの指導を受けることもあります。
外科的治療は、「骨組織の再建術」と「軟部組織の再建術」の大きく2種類に分けられます。
先天性の膝蓋骨脱臼は防ぐことはできませんが、外傷性の場合は膝に負担をかけない生活環境を整えることで予防ができます。段差や階段を歩かせない、フローリングなどの硬く滑りやすい床にはカーペットやマットを敷いてあげると膝への負担が少なくなり予防になります。
また体重が増えすぎても膝への負担が増してしまうので、体重管理も重要です。
関節の痛みの場合
関節の痛みを訴えている場合、関節炎が発症している可能性があります。また、早期発見が重要で発見が遅れることで重症化するケースもあるので、次にあげる項目に少しでも当てはまることがあれば、すぐにでも動物病院へ連れて行きましょう。
- 歩くときに足を引きずる
- 以前ならよく動く状況であるのにじっとしている
- 立ち上がる時に辛そうにしている
- 散歩に行きたがらない
- 「歩く、走る、遊ぶ」ことをしたがらない
これらの症状は、日頃からよく愛犬を観察していればすぐに気づくかと思います。
関節炎とは、その名の通り関節に炎症を起こす症状で、関節を動かしづらくなったり、痛みを伴ったり骨が変形することがあります。関節炎が重症化してしまうと、完治させるためには基本的に手術を受ける方法のみになります。また、リハビリも必要になります。
手術以外では、「関節炎の原因の改善」や「痛みを和らげる」という治療がメインとなります。
犬のてんかんが理由で吠える場合
てんかんの発作中や発作後に「ギャンギャン」と犬が吠え続けるケースが多々見受けられるようです。てんかんとは、脳の神経細胞に異常なほどの興奮がおこり、体のコントロールがきかなくなった状態のことです。
- 手足または全身や顔面がけいれんを起こす
- 意識をなくす
- おしっこやうんちを漏らす
- 体を仰け反り口から泡を吐き意識を失う
上記3つは軽い症状ですが、4番目は重い症状となります。発作の後は数分で普段の状態に戻りますが、しばらくフラフラしたりすることもあります。
初めて発作を起こした場合はとても驚かれるかと思いますが、落ち着いて様子を見て早急に獣医さんに診てもらってください。
原因
原因は大きく2つあると考えられます。ひとつは「特発性(原発性)てんかん」で、原因が分からないものです。
遺伝的な要素が強く、犬のてんかんのほとんどは特発性のてんかんだと言われています。ダックスやレトリバー系は特発性てんかんが多い犬種のようです。
そしてもうひとつが「二次性(症候性)てんかん」です。怪我などの外傷による後遺症や脳腫瘍などによって発生するてんかんで、これらが原因となります。二次性のてんかんは、その病気を治療することで回復することもあります。
対処法
てんかんの発作は、犬が眠っている夜間や早朝に起こることが多いのですが、てんかん症状が起きているのを発見したらまずは慌てずに発作が治まるのを待ちましょう。
ただし、おう吐などの症状がある場合は、吐しゃ物で気道が詰まって呼吸困難が起こらないよう、気道の確保が必要になります。口の中に吐しゃ物や異物がある場合は、取り除いてあげましょう。その際は、指を入れ他時に噛まれることあるため、注意して行いましょう。
てんかんの疑いがあり病院を診察する際には、どのような症状があったか、何回発作を繰り返したかなどの状況を詳しくメモしておくことも大切です。また、発作が起きている間、精神的に辛いかもしれませんが、愛犬の動画を撮影するのも診断するにあたり、貴重な資料になります。
てんかん重積について
このような発作が繰り返し発生すると、脳に深刻な障害を与えることもあり、ついには命に関わる危険な状態に陥る場合もあるので、油断は許されません。
てんかん発作が30分以上続く場合や1日に3回以上起こるときは「てんかん重積」と呼ばれ、通常のてんかんとは違い、脳に外傷や中毒症状がある場合もあります。早急に動物病院での治療を行ってください。
治療方法
てんかんの原因が他の病気による症状のひとつであれば、まずその病気の治療後に、てんかんの原因を調べる検査が必要になります。問診や身体検査、血液検査、脳波の検査等を行い、診断してもらいましょう。問診の際には、先ほどあげた症状のメモや動画などを持参してください。
原因がわからない突発性てんかんの場合は、薬での治療となります。抗てんかん薬を用いますが、薬には常に副作用があり、完治は難しいということも覚えておく必要があります。
レイジシンドロームのために吠える場合

今まで大人しかった愛犬が、突然他の犬や人間に対してひどく攻撃的になり噛み付いたりした場合、「レイジ・シンドローム」を疑いましょう。別名「突発性激怒症候群」とも言われます。
犬が吠えたり噛み付いたりする理由として、例えば、自分の守るべき領域であるサークルの中を見知らぬ人に踏み入られたり(縄張りを守る)、見知らぬ人が怖いから触られたくない、などが挙げられます。
しかし、この病気は何も理由がないのに突発的に怒り出して、人間や他の犬に対しても非常に危険な行動に出る疾患です。飼い主でさえ、その症状が発症すると噛みつかれることもあります。
突発的にその状況が起こったとき、まるで発作が出たように見え、実際、わんちゃんの脳の感情をコントロールする部分に何らかの異常が認められると言います。
発症しやすい犬種
元々、イングリッシュ・スプリンガー・スパニエルという犬種に多く認められた為、スプリンガー・レイジと呼ばれていたそうですが、その他でもコッカース・パニエル、プードル、ゴールデンレトリバー、ドーベルマンでも多く見られ、遺伝する可能性があります。
レイジ・シンドロームの症状
人間が激怒するように、わんちゃんも凶暴化しキレた状態になります。何の前触れもなく発作的に起こり、側にいる人や犬、モノなどに襲いかかるので注意が必要です。
この状態は数分から場合によっては数時間続くこともありますが、しばらくするとまた通常の状態に戻ってケロっとしているのが特徴です。
発作中は、ギャンギャンと吠えたり、歯をむき出しにして噛み付いたり、モノを破壊したり、瞳をかっと見開いてまるで別人になったかのように、完全にコントロールを失った状態になります。
飼い主さんは初めは単なる躾の問題と勘違いしていることが多いようですが、レイジ・シンドロームの疑いがあるようならなるべく早く動物病院に連れて行ってあげましょう。
原因と診断・治療法
ある研究では、脳の興奮を落ち着かせる「セロトニン」という脳内伝達物質の量が低下する事が原因で発症するとも言われています。レイジ・シンドロームの場合、その発作は躾などでは抑制できないので、動物病院での治療が必要になります。
脳の腫瘍があるせいでそのような発作が起きる場合も考えられますので、一般的な血液検査とレントゲン検査、さらには脳のMRIを撮影することになります。また、脳波を取ることでこの病気の診断に役立つことが分かっています。
老犬や痴呆の犬が吠える気持ちを分かってあげよう

一般的に、犬がシニア期を迎えるの7歳頃からです。個体差はありますが、10歳を超えると老化現象が大きくみられるといわれています。老犬になるとワガママになって吠えたり、認知症が理由で夜鳴きするようになるわんちゃんがいます。
無駄吠えとも言われていますが、それにも理由や原因があり、愛犬からが必死にサインを送っているのかもしれません。老犬特有の吠えについて、理解を深め、受け入れることが大切なのです。


老犬が吠えようになった理由を理解しよう!
シニア期のわんちゃんに吠えることが多くなった場合、若い頃とは別の理由がある可能性があります。何故、無駄吠えが増えてしまったのか、愛犬をよく観察して理由を探っていきましょう。
ワガママで要求吠えする場合
構ってもらいたい、寂しいことを訴えて吠えることがあります。その要求に応えることで一時的に無駄吠えはなくなりますが、吠えれば構ってくれると覚えてしまい結局は対処になりません。老犬は頑固になりがちなので、若い頃のようにすぐ躾けられるようにはなりませんが、諦めずに対応しましょう。
不安で無駄吠えする場合
老化により視力・聴覚・嗅覚が衰えることで、精神的な不安を感じやすくなります。飼い主さんの存在が近くにあるだけで不安も和らぐので、就寝時などは側で寝かせてあげたりするのも効果的です。優しく声かけしたり、撫でるなどのスキンシップをとってあげましょう。
身体的な理由で吠える場合
吠え+どこか痛がっている仕草をするのを発見したら、病気や怪我の可能性がありますので、すぐに動物病院で診察してもらいましょう。高齢により、体がうまく動かせなかったり、関節痛が出ることがあります。変な歩き方をしていないか、足に異常がないかをチェックしましょう。
また、次項で説明する認知症の疑いがある場合も、なるべく早く獣医さんに相談しましょう。
犬がボケると夜中にひどく吠えるようになる(夜鳴き)
上記であげた以外にも、老犬が吠え続ける場合、認知症・痴呆症が疑われる可能性があります。認知症になると、昼と夜の時間感覚も狂ってしまい、夜中に吠えること(夜鳴き)があります。
鳴き方としては「ワオーン」という単調な鳴き方を繰り返し行います。愛犬の吠え方を、注意してみておきましょう。
認知症による夜鳴きが起きた場合は散歩などで朝日を浴びさせる、夜は自然と室内を暗くするなどして、昼、夜のバランスを戻す工夫をすると効果的です。
- 昼夜逆転している
- 夜中によく夜鳴きする
- 同じ場所を何度もクルクルと回る
- 一点をじーっと凝視している
- 食欲が過剰に増えた、または下痢気味である
- できていた「おすわり」「待て」などが全く出来ない
- トイレ以外で粗相してしまう
などがあります。いくつか当てはまったら認知症の可能性がありますので一度病院での診察をおすすめします。
認知症の犬との付き合い方
認知症には、様々な原因がありますが、老化が進むことによって脳細胞の一部が死滅したり、萎縮したりすることで発症します。
残念ながら、認知症による脳の萎縮や死滅部分の再生は出来ませんが、残された脳細胞がなるべく衰えないように、症状の進行をある程度抑えることはできます。そのため、早期発見がとても重要になります。一日でも早く治療できるように愛犬がシニア期を迎えたら上記であげたサインに注意するようにしましょう。
また、認知症を発症したわんちゃんは、孤独感を感じることが多いようで、赤ちゃん返りをしてしまうケースも見られます。わんちゃんの最期まで見守ってあげるのが飼い主さんの務めです。愛情を注いであげて、その不安感を少しでも解消させてあげるように接しましょう。
まとめ
犬が急に吠えるようになった場合、単なる無駄吠えで済ませるのではなく、まずはその状況や吠え方を観察してあげることが大事なんですね。
お医者さんも定期的な健康診断などはしてくれるかもしれませんが、一番は近くにいる飼い主さんが普段からわんちゃんをどれだけ見てあげられているかが、わんちゃんの健康にとって重要なのだと思います。
- 普段から健康チェックをまめに行おう
- 吠えるのはわんちゃんにとってのSOSかも。病気でないか疑おう
- 様々な病気の対処・治療法をしっかり覚えよう
- シニア犬との付き合い方を改めて考えよう
普段からわんちゃんの健康チェックや吠え方、鳴き方の観察を行っていれば、万が一病気や怪我になったときでもすぐに病院に連れて行ってあげることができます。一番よくないのは無駄吠えだと思って無視したり叱ったりすることです。

病気やシニア犬についてなど、難しく重たい内容でありましたが、少しでも役に立てる記事になれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。














