こんにちは、優太です!
実は先日、同じ愛犬家の友人から慌てた様子で電話がかかってきました。何事かと思い、電話を取ると…
「優太君!大変なんだ!今犬の爪を切っていたのだけれど、血が出ちゃってとまらないんだ!」

僕がそう聞くと、友人曰く「ぎゃん!」と悲鳴を上げたとのことでした。ちなみに言うと、友人はワンちゃんを飼うのは初めてで、今回の爪切りも自分でチャレンジ!ということで、道具は一式用意したものの、肝心の止血剤を忘れてしまっていたようで…。

「止血剤ってなにそれ!」
このような状態でした。どうも、彼はワンちゃんの爪切りの際、深爪をしてしまったようです。私も最初は慣れず、実は一度だけ友人と同じ失敗をしてしまったことがあります。突然の赤い液体を見れば、慌てますよね。幸い、友人のワンちゃんの場合は、私が近所に住んでいたので、猛ダッシュで止血剤をもって急行したおかげで、大事にはいたりませんでした。友人の道具の一式に、止血剤はなかったわけですが、人間の爪のように薄くないワンちゃんの爪。ワンちゃんを飼う初心者の友人は、おそらく人間と同じような感覚で切ってしまったのでしょう。
そこで今日は、爪切りとするときの注意点を交え、わんちゃんの爪の役割や構造についてお話をしていきたいと思います。
何故!?犬の爪を切ってあげただけなのに、血が出てきた!!

犬の爪の中には、血管と神経が通っています
犬の爪には、血管と神経が通っていること。
これは、爪を切るときにおいて、先ほどの友人は「愛犬爪切り出血事件」を機にわかったようです。今は近所のトリマーさんに爪切りをお願いしているそうですが、爪切りの処置を含めて、犬の体の事はわからないことだらけです。わかってからの対処法として、友人は自身の手で爪切りをするのではなく専門家にお願いをする選択肢をとりました。
犬の爪には、血管に加えて神経も通っています。こまめに切っていれば問題ないのですが、しばらく切ってなかったり、そのまま放置すると、血管と共に神経も一緒に伸びていきます。いつものように切ろうと、忘れたころに…となってしまうと、神経も伸びているため、犬も痛い思いをし、飼い主も血を見てパニックというわけです。
また別の友人のケースですが、友人は年末、愛犬である黒パグの女の子の爪をお母様と一緒に切っていたそうです。その時は、ニッパー式の爪切りで切っていたそうですが、黒パグの女の子の爪は黒かったため、血管の位置がわからず、
「まあ短くしとけばだいじょうぶでしょう」
という軽い気持ちで、おとなしい子なので穏やかにちょきちょき…と切っていたのも束の間。見えなかったのが災いして、血管もご一緒にちょきんとしてしまったとのことでした。年末のため病院もやっておらず、さあどうしようと慌てていつもお世話になっているトリマーさんに電話をしたところ、応急処置としてお線香の灰を塗ってから、出血している部分を圧迫するという方法でした。幸いその時は止まったからいいものの、年末で病院がやっていないときや、トリマーさんたちが忙しい時期。きちんと、私も含めてですが、愛犬の管理は日頃からきちんと油断せず丁寧にしていかなければならないですね。




爪を長く伸ばすと神経と血管も伸びてきます
神経と血管は、爪が伸びると一緒に伸びていきます。ですので、あまり長い期間爪を放置しておくと、後々切る時に、切る範囲も狭まるため、決めたサイクルと伸びた頃合いを見極めて整えていくことが必要となってきます。
わんちゃんの爪は、猫の爪とはちがい出し入れができません。研ぐということもしないので、散歩も大切な爪を整える大切な場です。歩きながら、アスファルトで削られていくので、ある程度は整えていることは確かですが、あくまで整えている程度なので、散歩にだけ頼らず、きちんとケアをしてあげる必要があります。
また犬の爪は伸びると、血管も神経も伸びると説明しましたが、どこまでも永久に伸びていくということはありません。ある程度一緒に伸びると止まりますが、故意に深爪をして血管と神経まで切っていると、逆に退行していきます。
痛み、バイバイ!出血させない、犬の爪の切り方

犬の爪を切る頻度

愛犬の爪を見て悩むこと数分。カチャカチャ音をたてながら歩いているマロンとラテは、私の悩む顔などを気にすることなく家の中を走ったり歩いたり…。でももう切ってからいつだっけと少し思い出してみれば、もう一か月は切っていません。でももう切ったほうがいいかなと思ったのには、きちんとした理由がありました。それは先ほどの、家の中を歩く足音です。わんちゃんの爪は、先ほど最初のほうで言った通り、弧を描くように伸びていきます。伸びると、自然と床と触れることになり、音をたてながら歩くことになるというわけです。実はこれが、
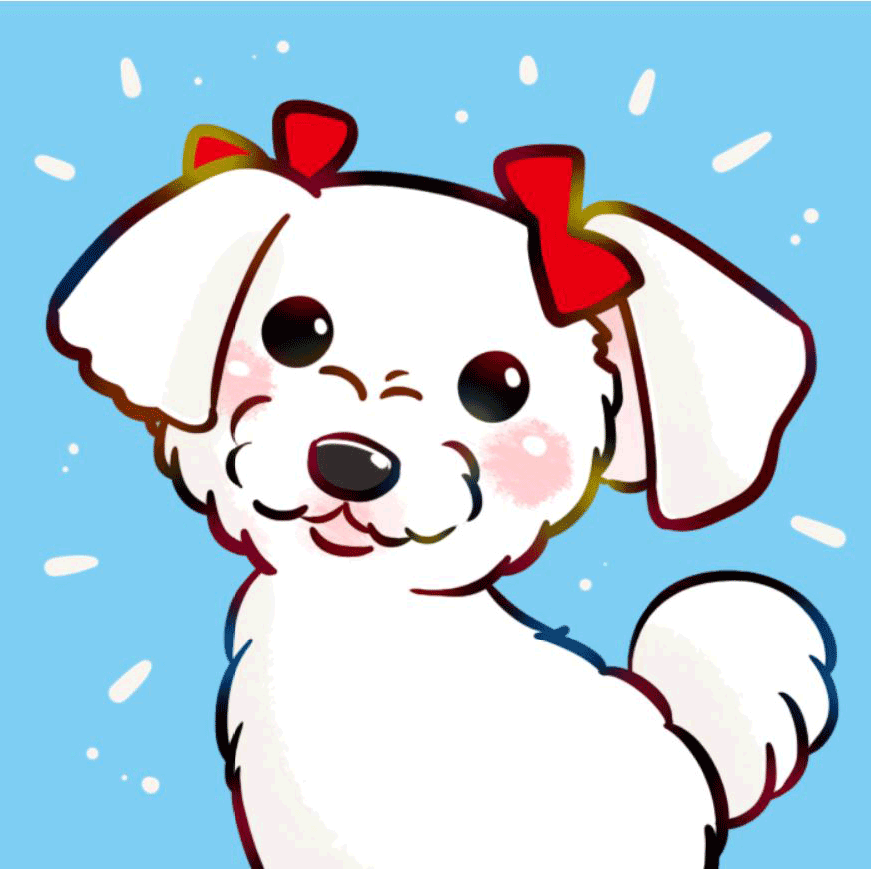

という合図。切り頃と言ったら言い方は悪いですが、切った方がいいサインなのです。
特に、今ではあまり使わることのない狼爪に関しては、長く放っておくとそのまま丸く伸びていき、肉球に刺さったり、ケガのもとになってしまいますので、注意が必要です。平均的に、犬の爪切りの頻度は月に一度。家庭で飼われている犬の場合だと、3週間に一度。犬種にもよりますが、お散歩の頻度が少ない犬だと月に二回という場合もあります。フローリングの上を歩いている時の足音が合図であったりするので、普段の家の中での様子を気にしつつ過ごしてあげることも爪切りのポイントのひとつです。
血管の位置を確認しよう



「どうして白い爪だから血管の位置がわかったの?」
と思う飼い主さんは多いかと思います。白い爪だと血管はわずかにピンク色に見えて、伸び幅と血管の境目が分かります。ですので、家で爪を切るときはそれを目印に短く切ることができます。爪を切ったら、ただ切るだけではなく、きちんと丸くなるようにやすりをかけてあげましょう。やすりをかけないままだと、犬自身が自分の体を掻いているときに目や耳を傷つけてしまったり、飼い主の皮膚を傷つけてしまったりしてしまいますので、丁寧にやすりをかけてあげてください。
黒い爪の犬を爪切りするには?
血管のを見分けるのに大変なのが、黒い爪の子たちです。慣れていても、思いきり切るのは禁物です。黒い爪の子のほかに茶色い爪の子もいますが、そういった犬の場合は「少しずつ慎重に」を心がけて切り進みましょう。切り進んでいって、

と、切りながら感触でわかったら、そろそろ切らなくても大丈夫という合図です。さらに、断面に白い膜のようなものが見えたら、その先に血管があるという証拠なので、爪切りは終了にしてやすりをかけて終わりにしましょう。
備えあれば憂いなし!止血方法も知っておこう

止血剤を使う方法…それって痛いの?
止血剤は、爪切り時の出血トラブルにおいては必須です。むしろ、爪切りに慣れていないうちはそばに常に置いておくことをおすすめします。動物病院で売っている場合もありますので、事前に購入しておくと良いかと思います。しかし、トリマーさんの多くが愛用している「クイックストップ」という止血剤などの、即効性のある市販の止血剤は確かに効果は高く、血の止まりも早いのですが、代わりに患部に直接塗布していわば焼いて止めるような形になるので、少々痛みを伴います。
止血剤の代用となるもの


血が止まらなくて焦ってしまって、でも病院もやってない…。そんな時はたくさんあるかと思います。家にあるものでできる代用品のひとつに、小麦粉を爪に塗るという方法があります。お線香の灰を代用する方法もありますが、犬が灰を舐めてしまう場合があるので、気を付けて行う必要があります。他には。焼却止血法というものがあります。出血が怖いと感じる場合には、トリマーさんやあらかじめ病院の先生に切ってもらえるよう普段から爪を切るタイミングのサイクルを作っておくと、より良いです。

爪は伸びすぎると、犬自身が自分で自分を気付つけてしまう場合もあれば、犬同士で遊んでいるなかで相手の犬の目を気付けてしまったり、ケガをさせてしまったりしてしまいます。パグやチワワなどの目が大きな犬種の場合だと、子犬同士で遊んでいたら傷ついてしまったという例もあるほどなのです。実際友人が黒いパグを家族に迎える際、当日なって引き取り日の延長を言われたそうです。理由をブリーダーさんに聞いたところ、子犬同士のじゃれあいで左目を、相手の兄弟犬の爪で傷つけてしまい、治療をしているとのことでした。犬同士でも、人と犬とでも痛い思いをしないためにも爪切りは、とても大切なケアの一つなのだと私は話を聞いた際、思いました。
犬の爪の出血が止まらない!どうしたらいいの!?

「爪切りをしていたら、血が出た!止血剤も効かない!どうしよう…」
となった時まずやることとしては、爪の付け根を圧迫し、切った断面も押さえるという方法です。切りすぎた場合によって起こる出血事件の対処法として挙げられるのは圧迫法です。それでも止まらなかったら、先ほどのべた焼却止血法を行うという最終手段をとって血を止める方法もあります。一番はお医者さんに診てもらう事です。きちんと治療をしてもらうのが最善ですが、家で切る場合は、
「少しずつ、丁寧に、ゆっくりと」
を基本にしましょう。



爪切りにおいて、ニッパー式の爪切りを使う飼い主さんが多いかと思いますが、実は犬にとって、あの切られた瞬間の「バチン!」と響く瞬間が嫌な子もいます。人間のように、じっと静かに切ってもらっている子って、お家では慣れていない限りはいないかと思います。動いた瞬間に誤って…というパターンもあります。
「急に動いたから思い切りきっちゃった!」
という例もありますが、犬はじっとできる子とできない子の割合として、できない子の方が多いです。家で切る人の中では二人がかりでおさえながらという家もあるでしょう。それでは悪循環ですし、ますます自宅での爪切りが難しくなっていきます。
「一度出血事件に遭遇してから切るのが怖くなっちゃった…」
と、少しでも感じた方は、トリマーさんかお医者さんに切ってもらうことをおすすめいたします。
爪を出血した後は、お散歩に注意しよう

出血のあとでも、飼い主が散々慌てたあとでも、

と、変わらず楽しく過ごしているのが全国の愛犬の皆さまだと思います。こちらの心配をよそに、痛みと出血がなくなれば外に繰り出し、いつものように楽しくお散歩をすることでしょう。しかし、私が、出血後にお医者さんに連れていくことを推奨するのはそういった理由があります。それは、傷口から菌が入ったことによって起こる感染症です。散歩道、血がせっかく止まったのに、アスファルトに爪が当たってまた出血だなんてことになったら元も子もありません。見えないばい菌もいるので、出血後のお散歩は注意が必要です。


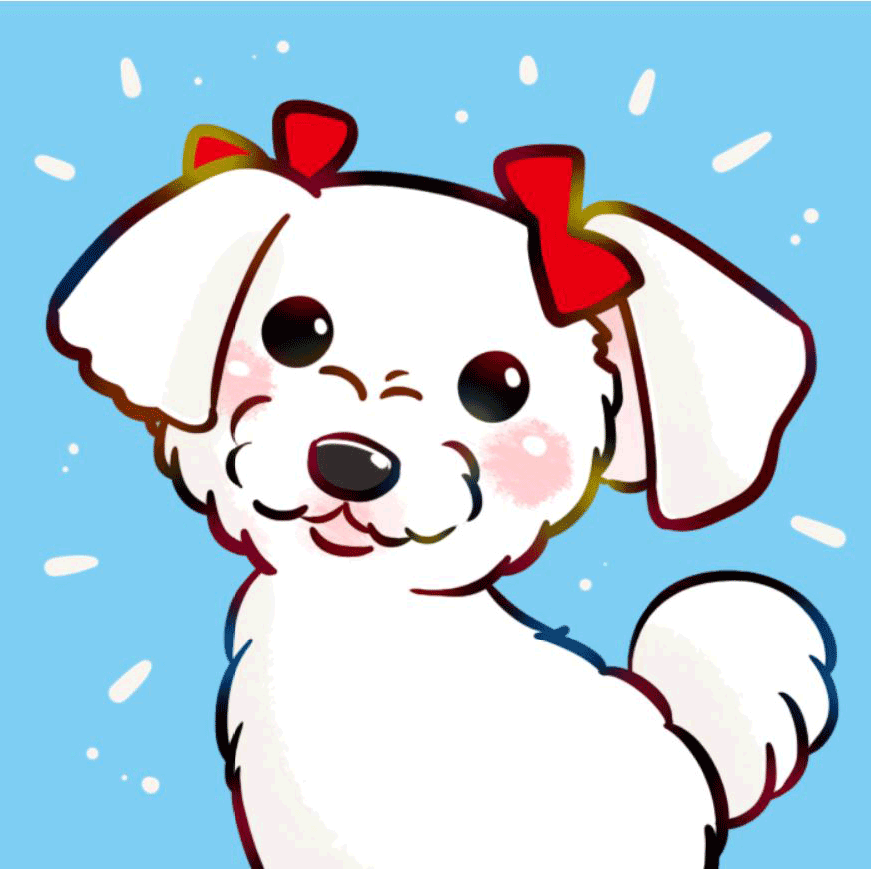


【番外編】犬の爪から内出血!? どうしたらいい?

犬の爪、特に白い爪の子の爪を見ていて見つかるのが、爪の付け根から黒くなっている部分。それは内出血です。痛そうに歩いていたり、気にしている様子が無ければ得に問題はありません。心配であれば、お医者さんに連れて行って良いでしょう。グラグラしていたりしていれば、爪を抜くという処置も必要になってきます。爪の内出血は、散歩の多い大型犬や、運動量の多い犬種などに見られる現象です。そういった場合は自然現象なので問題はないですが、他の原因では、まさに運動のしすぎといった場合も考えられます。逆に、黒い爪の子であるとわかりづらい点があるので、黒い爪や茶色い爪の子は、特に気にしてあげることが必要です。
少しでも、小さなことでも、気になる症状が起きたら、お医者さんに診せることをおすすめします。犬は、人間のように、言葉を出して症状を伝えることができないので、普段から様子をきちんと見て、普段との違いを見極められるよう、スキンシップなどのコミュニケーションを重ねていきましょう。
犬の爪は、人で言う靴であり、サッカー選手でいうスパイクシューズ。彼らの瞬発力を支えているのは、その地面に触れている4つの足という名の靴です。その靴には、爪という大事な道具が備わっています。
そして、わんちゃんのおやつのである犬用の骨を食べるとき、押さえることにも使っていますよね。
それから無我夢中で行っている穴掘り。

と声が聞こえてきそうな勢いで、爪と腕の力を使って掘っている姿を目撃する方は多くいらっしゃると思います。あと可愛い例をあげれば、飼い主に頭をなでてもらっている最中に中断された際、爪を使って、


と、撫でてもらえるよう催促するために使ったりすることもあります。あれ?これは我が家のマロンとラテだけでしょうか。
犬の爪は道具としてつかう以外にも、コミュニケーションをとることにつかったり使い方は多種多様です。先祖が狼であるため、野生で生きていくための使い方としての印象を受けがちですが、案外人が思っているよりも、爪の使い方を分かっているのは犬自身なのかもしれません。
犬にとっても、人間を含めたすべてに動物にとっても「足は第二の心臓」と言われています。移動をするにしても、骨を食べるときも、何かをする時には人間と一緒で大事な部分なのです。
爪切りと血管のお話で、忘れてはならない犬の先祖に関わる存在があります。
ひっそりといる5本目の指がいます。爪が伸びてくると目立ってくるのですが、人間でいう親指の部分にあたる「狼爪(ろうそう)」という爪があります。この爪の目立ち具合は犬種によりけりで、先祖である狼に近い種であるシベリアンハスキーやアラスカマラミュートは、狼爪があることがよくわかります。ちなみに、ラテとマロンにも分かりにくいですが、よく見るとひっそりとかわいく存在しています。狼爪は、進化の過程を証明する体の一部であることを示していて、その昔獲物を食べるときなどに狼爪をひっかけたり、道具のひとつとして使われていたそうです。
犬の爪の血管が通っている。爪切りも、人と違って工具のような器具で切る。それをしかも、血が出ないように慎重に。昔の狼たちを含め、本来ならば犬の爪切りは不要です。外で暮らしていた彼らにとって、普段の生活のかで自然と削れて、整えられていたからです。ところが、最近は家で飼われる犬が多くを占めています。家の中はアスファルトでしょうか。ザラザラとした砥石のような地面でしょうか。そうじゃないですよね。近年、畳の家も少なくなり、フローリングの家が多くなってきました。その上には何を敷いてますか。カーペットであったり、絨毯であったり、犬はフローリングでの歩行だと腰を痛めたり足を痛めたりしてしまいます。家の中であれば、爪も研がれる機会もないので、伸び放題になってしまうのは想像がつきます。滑ってころんだりしないように、本来なら愛犬の健康のためにとやっていることが、実は爪切りに影響しているんです。
しかし、月に一度でも切るというサイクルを作り、行きつけのトリマーさんやお医者さんを見つけておけば、

と、気付くことができます。
爪の伸び頃を、ご存知でしょうか。呼ぶと、遠くから、
「カチャカチャカチャカチャカチャカチャ…」
爪の音をたてながら嬉しそうに、しっぽを振ってやってくる姿。愛らしいですよね。私もうれしいです。呼んだらしっぽを振りながら走ってくる姿は、私も大好きです。ですが、その音が実は「切り頃ですよ」という合図なのです。その時、お手!なんて言って見て見てください。弧を描いて伸びていませんか。
出血事件が自宅で起こる前に、そういった「切り頃」を見定めておくと良いかと思われます。犬が爪を噛んでいるときありませんか。それはストレスの合図なのですが、爪を噛んで割ってしまう子もいます。爪が長いと、余計噛みやすく割れやすいです。そのような時、爪も伸びて血管も伸びていたら、違うところで出血事件が起きて大パニックになってしまいます。
犬の爪は、人間でいう指に等しいと考えた方が妥当なのかもしれません。普段生活に使う人の指にも血管が通っている事と同じで、穴掘りに使うのも、骨を食べるのも。走るのも歩くのも。人と同じで爪は、人でいう指であり手であり大事な部分。そのような大事な部分から血が出ないよう、大事に大事に整えてあげることは、飼い主であり家族ある私たちの義務です。
「爪切りなんかめんどくさい」
そう思ったあなたの爪はどうなってますでしょうか。それから愛犬の爪を見てください。愛犬も、
「そろそろ私の爪なんとかしてください」
と、思っているかもしれません。人にとっても犬にとっても大事な爪を、命と同じくして大事にしていってあげましょう。
わんちゃんの爪の役割と血管について

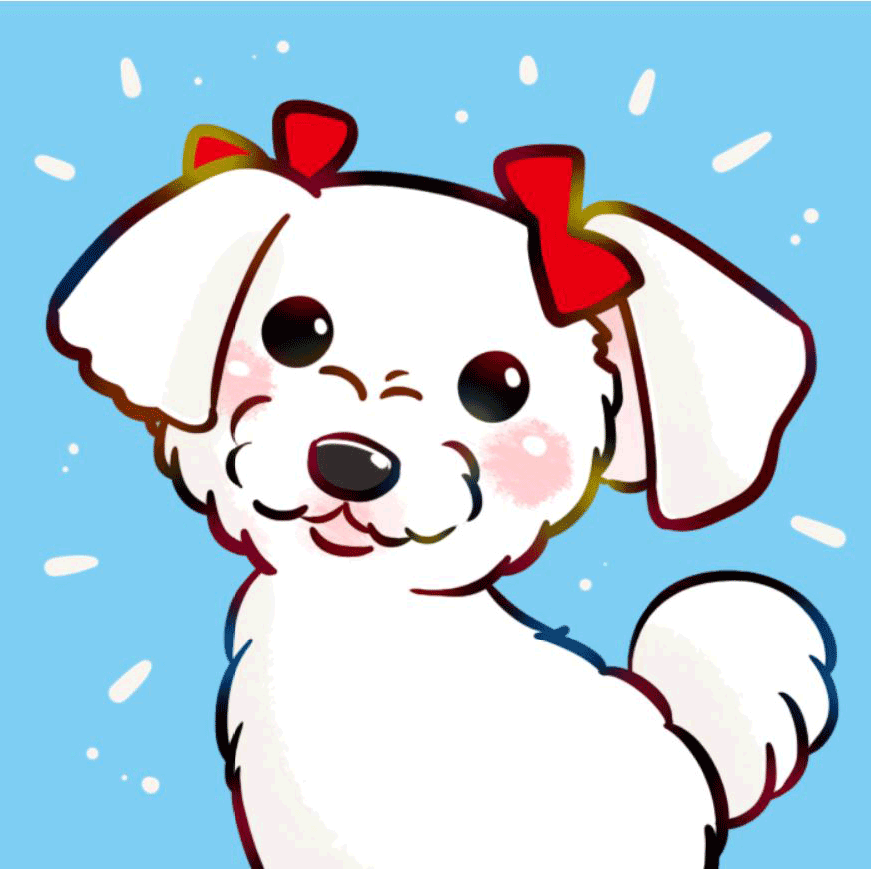





ここまで犬の爪の役割と血管について述べてまいりましたが、ひとつ大きく言えることは、犬も人間と同じくして「手足を使って生活している」ということです。犬の爪に血管が通っていることと繋がります。人間も、生活で使う体の部分には、血管も神経も通ってますよね。犬の爪もそれと同じです。
上記で述べた爪切りについてですが、実は知人の女性に教わったことなんです。その知人は、自分の病気の治療をしながら働いています。ですので、体調を崩すこともしばしば。ある時、一週間以上体調を崩し、仕事に行くのがやっとという時が続いたそうです。その方も犬を飼っています。日常生活もやっとの日々で、ふと自分の足の爪を見たところ伸びていましたが、面倒で切るのも億劫でした。「めんどくさいなぁ、自分のは明日でいいや」と思っていた時、ふと隣で寝ていた愛犬の爪を見たとき、まさに半月のように弧を描いて伸びていた爪を見たそうです。家族だからこそ、連動する愛犬と自分の体の変化。反省すると同時に、
「家族だからこそ、爪が伸びるのも一緒。寝るのも一緒。ごはんの時間もほぼ一緒。毎日一緒の時間を生きているのだから、すべてが一緒。きちんと見てケアしなきゃな」
と、思ったそうです。
最後のまとめ!
上記で述べた爪の役割として、大きく分けて6つ。
- 犬の爪には血管が通っていること。そして爪が伸びると血管と神経も伸びていきます。
- 爪を切るのは月に最低でも1回。
- 自宅で切る場合は、止血剤をお守りに。
- 血管の位置がわからないうえに、爪切りも慣れていない場合は専門機関に任せる。
- 「爪切り自分のめんどくさい」は「あなた(愛犬)の爪切りめんどくさい」です。
- 爪は日常生活の必需品。きちんとしたケアを!
犬の爪の役割は歩行、走行をふくめ、進化の末に今では足という「第二の心臓」を守るためのもの。「もの」という表現が合っているとは思えませんが、爪は彼らの毎日を支える大事な道具なのです。
そして血管は、飼い主の皆さまの管理の度合いを表現している役割もあるのかもしれませんね。












