皆さん犬の爪切りはどうしていますか。慣れた飼い主さんなら、毎月飼い犬の爪を、自分で切ったりしている事と思います。え?犬に爪切りが必要って知らなかった?それはいけません!飼い始めたばかりの方は、ご存知ないかもしれませんが、犬は定期的に、爪切りが必要なんです。
ワンちゃんの爪が伸びすぎると、歩くとだけでも床や地面に、伸びた爪が当たって動きづらいし、何かに引っ掛かけて怪我したりする、なんてことも考えられますので、爪のお手入れはとっても重要です。でも犬を飼い始めたばかりで、爪切りなんて自分で出来るのかな?と不安な方もいらっしゃるかと思います
既に犬を飼っている方も含めて、これから自分でも爪切りに挑戦してみようか、とお考えの方々に向けて、今回は失敗しない切り方を、ご紹介したいと思います。
爪から健康状態もわかる


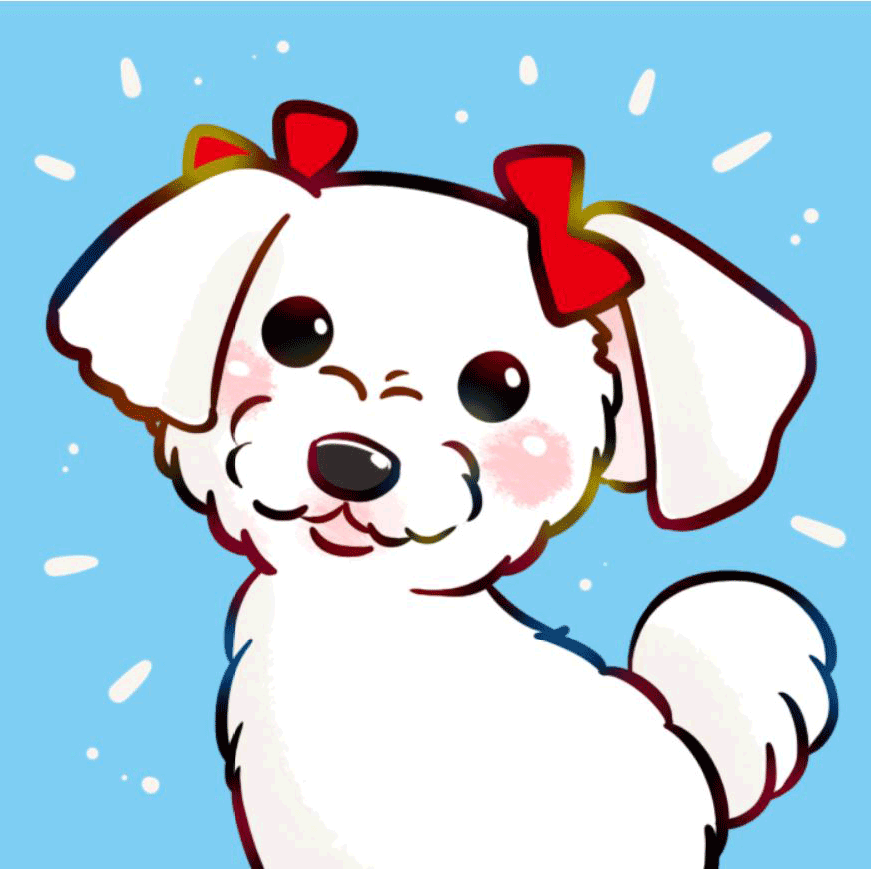
爪を切る目安は、およそ爪の先が、床に着く程度の長さになったら、そろそろ必要になります。いつも外で遊び回っていられるような環境だったら、その活動中に自然と爪も削られて適度な長さが保たれるんですが、室内飼いだとそのような機会は散歩のときくらいで、それだけだと伸びる方が速くて、削れるのが全然追いつきません。
人間も爪を伸ばし過ぎたり、割れたりしてると衣服などに引っかけて、怪我することありますけど、犬もそれは同じで、伸びたまま放っておくのは危険なんですよ。
それと犬の健康状態が、爪の状態からも判断できるって事はご存知ですか。例えば犬も人間も爪はタンパク質のケラチンから出来ていますが、栄養が偏ったりタンパク質が不足して、健康状態が悪化すると、爪が荒れて痛んだり、ボロボロになったりします。
つまり、爪の状態に異常が無いか見ることで、病気が重篤化する前の比較的軽い段階で、発見することもできる、ということですね。予防の観点からすると、犬の爪切りは定期的に、そして飼い主が自分でやった方がいいですね。
伸びすぎ注意!!爪の切り方はプロに学ぶ

犬を初めて飼う方だと、犬の爪ってどうやって切ればいいか、わからないですよね。そういう方が、いきなり自分でやろうとするのは、ちょっと危ないかも知れません。確かにネットで調べると、やり方を紹介しているサイトはたくさんあるので、それを見れば、何となく自分でも出来そうな気になる方も、いらっしゃるでしょう。
でも、ちょっと待ってください。それだと下手すると、ご自分のワンちゃんが、怪我してしまうかもしれませんよ。実際やったことが無いことを、知識が不十分なままやるのは、危険です。
そんなに難しいことでもありませんから、ここは安全第一で、慎重に手順を踏んでやっていきましょう。
切る頻度はどれくらい?
室内飼いしている犬だと、外飼いの犬と比べて、爪がこすれてすり減る機会も少ないので、爪切りの頻度は月1回程度と言われています。
犬の爪を切るには、道具を揃える必要もあるので、いきなり自分でやるのは、止めておきましょう。まずはペットサロンや、動物病院で爪を切ってもらうのをおすすめします。値段は500円~1000円程度で、かかる時間もたいてい5分~10分だから、気軽に利用できると思います。
動物病院を利用すれば、ついでに健康チェックも兼ねられるので、一石二鳥でもありますね。もし毎月出かけるのが億劫でなければ、わざわざ自分でやらなくても、動物病院に完全お任せにしてしまうのも、悪くない選択だと思います。

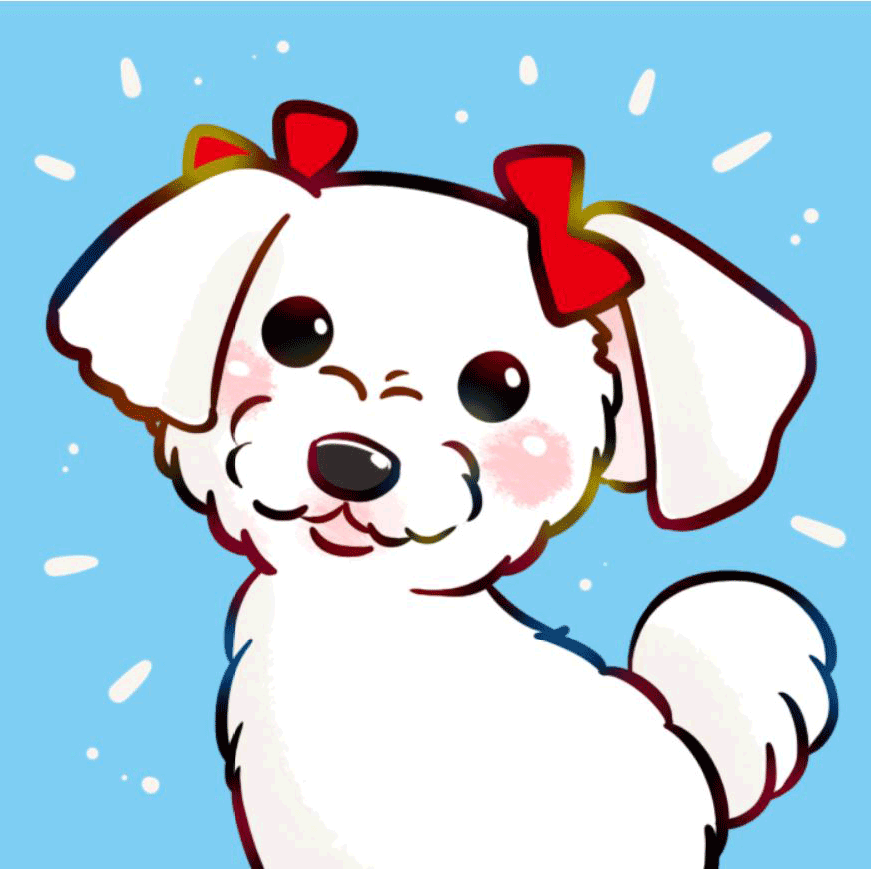

どこまで切るか?お手本の写真を撮ろう
自分で切りたい方は、動物病院やペットサロンで、やり方をよく見ておきましょう。不明な点があれば、その時よく質問しておくのもいいと思います。そして次が重要なんですが、プロが犬の爪を切った状態を、写真に撮っておくのです。
百聞は一見に如かず、と言いますが、ここで理想的な犬の爪がカットされた状態を、写真で記録しておけば、後になって自分でやろうとする時に、どこまで切っていいかが、視覚的にすぐ確認できて大変便利です。
当たり前のことですが、たとえネットに、犬の爪切り情報が山のようにあったとしても、自分のワンちゃんの模範的な、爪を切った状態の写真って自分で撮らない限り、どこにも無いですからね。さらに、出来れば切ってもらっている時の、動画も撮っておけば、後で手順を復習するときに、とても役立ちます。

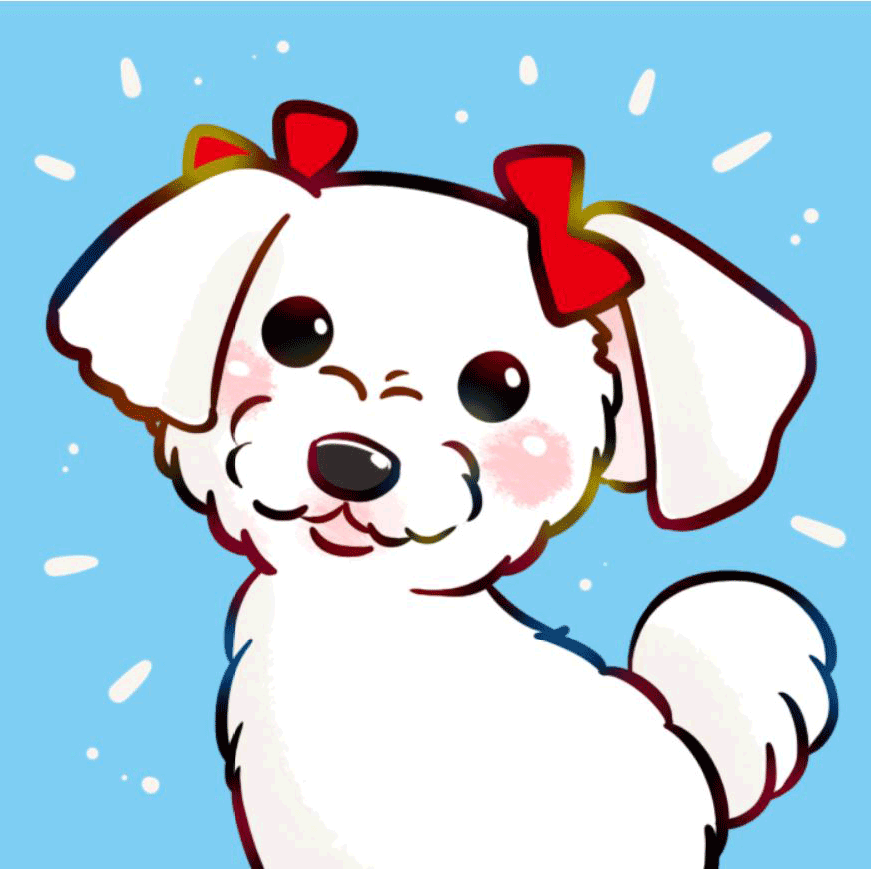

やり方は動画でも学べる
写真と違って、自分で動画まで撮るのは、さすがに難しいかもしれませんので、そんな方は復習のために、YOUTUBEなどの動画サービスを使って、爪の切り方を確認しましょう。写真は貴重な情報ですが、完成図しかないので、そこに至るまでの道筋が解りません。
でも動画なら、写真では抜け落ちてしまった、実際の爪切り作業のやり方を、順を追って理解出来ます。完成品の写真では足りない部分を補ってくるので、非常に役立ちますよ。もう切り方を憶えてしまったなら、写真だけで十分ですが、慣れないうちは、何度でも見て大いに活用して下さい。
自分で爪を切ろう


切り方を復習しておく
もう一度、写真や動画などでやり方や手順を十分復習しておきましょう。特に初めてやる時は、段取りを決めておくとスムーズに進めやすいし、万が一トラブルがあっても対処しやすいですよ。
保定する
爪を切っている時に、犬に動かれて、作業にならない事態は、避けたいところです。特に慣れないうちは、1人より2人で役割を分担することをおすすめします。1人が保定(犬が動けないような抱き方)を担当し、もう1人が爪を切る、といった具合だと作業もスムーズに進みますよ。
良い道具を使えば素早く切れる
爪切りが安物だと、切れ味が悪くて切りにくいです。時間もかかるし、後のやすり掛けの手間も掛かり大変です。切れ味悪いと、下手すると犬の爪が、割れてしまうこともあって、ワンちゃんへの負担が重くなってしまいます。
でも道具が良ければ、切り口綺麗に爪切りも早く終わって、やすり掛けもほとんど必要ありません。犬も飼い主もストレス少なく、値段以上の恩恵が受けられますよ。
使っているうちに段々と切れ味が落ちてきて、作業効率が悪くなってきたなと感じたら、新しいものとの交換をお勧めします。
もし爪切りを買っては見たものの、使いにくさを感じるようならば、別のタイプの購入も検討してみましょう。爪切りは毎月の作業ですので、一時的に出費が多くなったとしても、長い目で見れば、自分にとって使い勝手が良いものを使う方が、効率よく作業が出来て満足いくと思います。


切った後はごほうびも
飼い主も、いつもと違うことをするので、その只ならぬ気配が犬にも伝わって、爪切りを嫌がるかもしれません。爪切りの印象を、少しでも良いものに変えたいので、嫌がる犬には、切り終わったらごほうびをあげましょう。


切らずに削る
裏技的やり方ですが、自分でパチンとやるのが怖ければ、電動式の爪トリマーなんていかがでしょうか。これは爪切りと違って切断するのではなく、機械で爪を削っていくタイプなので、切り過ぎによる失敗がありません。
切らずに削ること自体は、電動でなくても自分でやすり掛けすれば、同じように出来ます。でもそれでは時間がかかってしまって、多くのワンちゃんは我慢できないと思います。
電動式トリマーは、それほど大きくないですが、動作音が出るし、削るときの振動もありますから、この音や振動をワンちゃんが怖がって吠えたり、逃げたりするようだと使うのは難しいです。でもそれさえなければ、過去に爪切りで失敗して、嫌がるようになったワンちゃんにも、有効かも知れませんので、検討してみてはいかがでしょう。

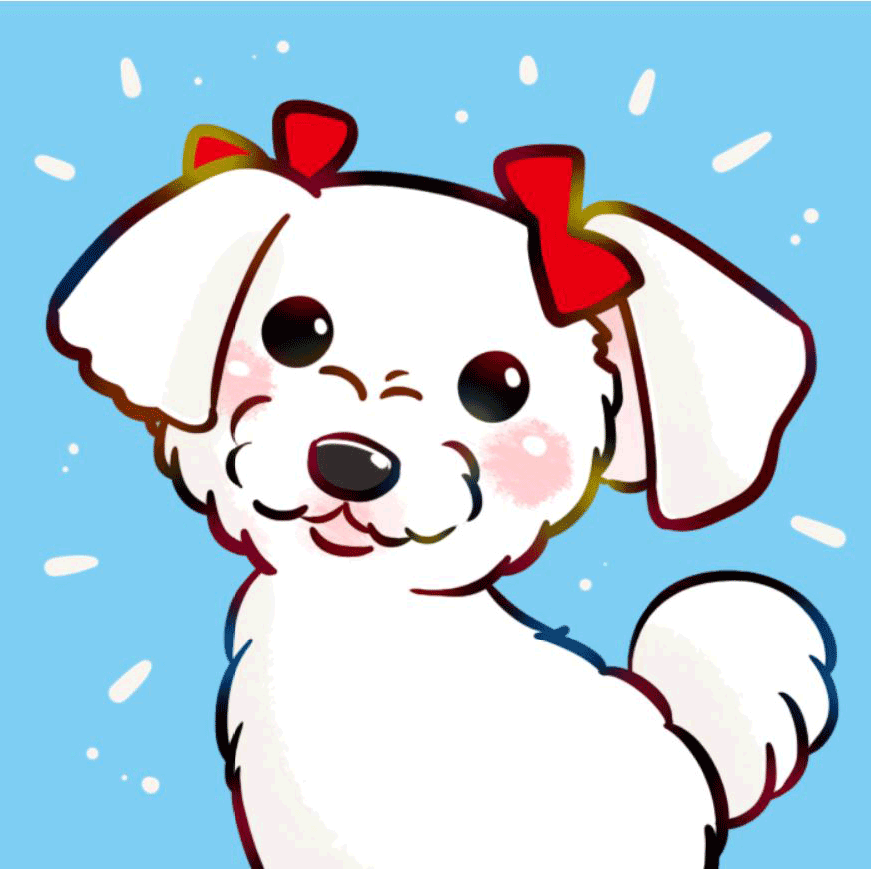


爪を切る上での注意点は?

切りすぎ注意
人間の爪と同様に、血管が通っているところは、赤みがかっていますので、そこまで切らないように注意して下さい。人間と同じ感覚で深爪すると出血の可能性もあります。白い爪の犬なら簡単に解りますが、爪が黒い犬だとちょっと見た目で判断が難しいです。
陽の光に照らすと見えるんですが、解りにくいと思います。どこまで切っていいか解らなくなったら、動物病院で切ってもらった時の写真を参照してみて下さい。
出血に備える
止血剤という便利なものがあります。でもこれは、ワンちゃんのためを考えると、あまりお勧めできません。確かに即効性はあるんですが、患部を焼くような止血法なので、すごく痛いのです。ですからよっぽども事が無い限りは使用したくないですね。
それよりも、どこの家庭にでもあるようなものを使いましょう。ガーゼやハンカチで、圧迫することでも止血できるし、片栗粉や小麦粉を、出血した爪に入れても、止血効果があります。血が止まったら、患部を洗浄して清潔にしてあげましょう。
まとめ
- 犬の爪の伸びすぎは怪我のもと。定期的に切る必要がある。
- 自分で出来なくても、動物病院やペットサロンで爪切りしてくれる。
- プロに爪切りしてもらって、自分がやるときのお手本用の写真を撮る。もし動画も撮れれば完璧
- 実際やるときは、事前に納得するまで写真や動画で復習する。どこまで切っていいかを十分確認。
- 良い道具は、作業をスムーズにする。段取りが整っていれば、大抵のことはうまく行く。
- 万が一のケガに備えて、止血の準備は必ずする。
- それでも自信がなければ、自分でやらずプロを頼る。
自分で爪を切るのは、段取りを踏めば、それほど難しいことは無いと思いますが、そこは生きてる犬が相手。ワンちゃんの個性もありますし、何が起こるか解らないので油断はできません。
道具もそろえて準備万端で、いざ実行という時になって、やっぱり自信が無い、と思ったら無理せず止めておきましょう。安全第一です。
「ここまで準備したんだからやらなきゃ」、なんて頑張る必要はありません。飼い主がそんな状態では、犬も怯えて多分うまく行きません。人間だれしも得手不得手というものがありますから。そんな時は、プロに任せるのも良い判断ですよ。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。














